Special 【例文ありで即使える】講演会の終わりの挨拶・謝辞例文集
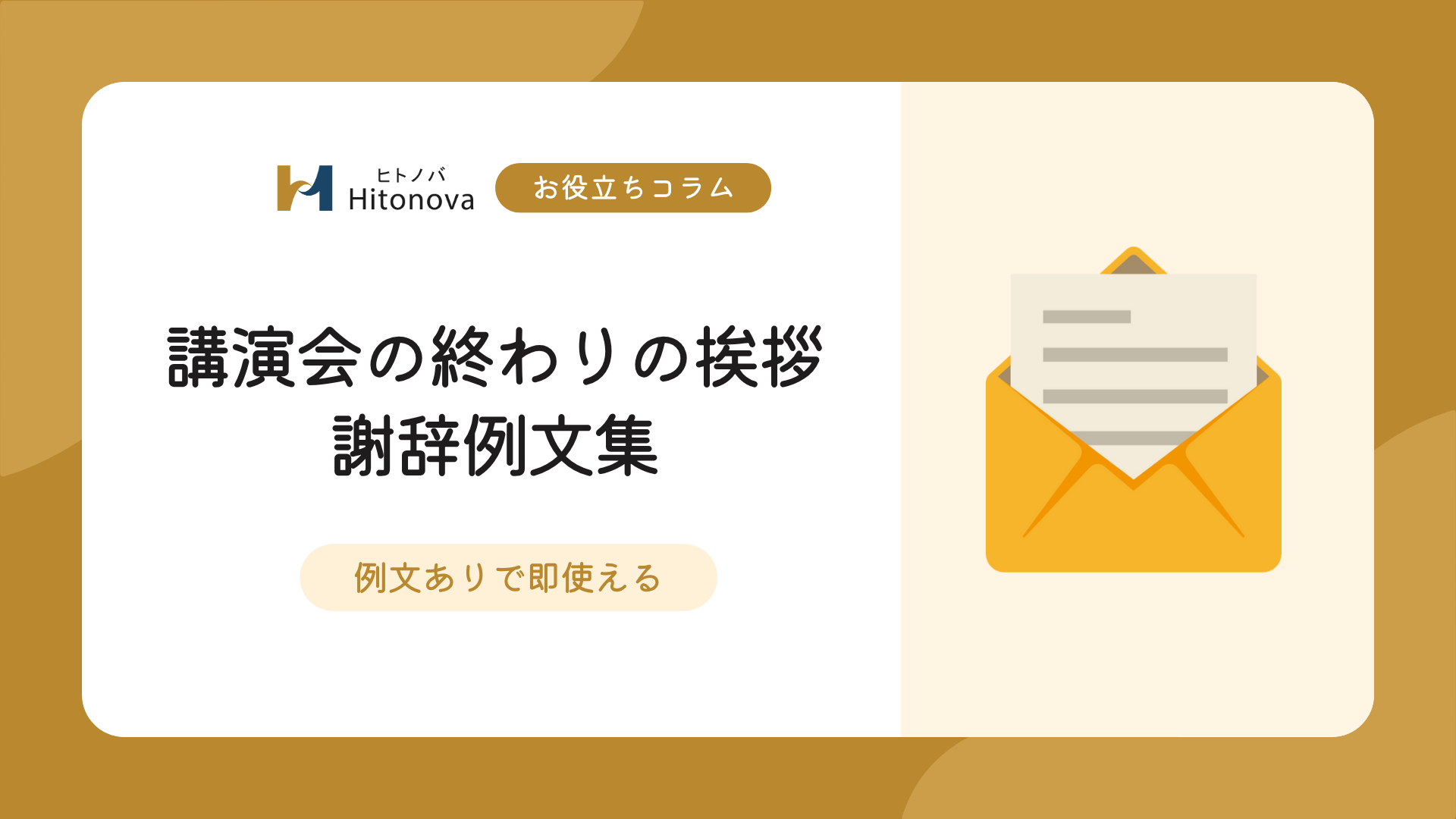
講演会の締めくくりに行う終わりの挨拶(謝辞)は、会全体の雰囲気を整え、講師や参加者へ感謝の気持ちを伝える大切な時間です。
短い挨拶であっても、その一言が講演会全体の印象を左右することがあるため、言葉選びや構成、マナーには細やかな配慮が必要です。形式的になりすぎず、聞き手の心に残る表現を意識しましょう。
近年では、オンライン講演会やハイブリッド形式のイベントも増え、講演会の終わりの挨拶や謝辞の伝え方も多様化しています。画面越しに思いを届けるには、声の抑揚や話すスピード、カメラ目線、通信環境への配慮など、従来とは異なる準備も求められます。どのような形であっても、相手を敬い、誠意をもって感謝を伝えることが何より大切です。
本記事では、講演会の謝辞の基本構成・話し方のコツ・実際に使える例文までをわかりやすく解説します。
講演会の主催者や司会者、学校・企業で挨拶を任された方など、どなたでもすぐに使える内容です。読んだその日から役立つ実践的なポイントを、ぜひ最後までご覧ください。
あなたの講演会を、もっと印象的に
謝辞だけでなく、企画全体を成功させるための講師選びもお任せください。
経験豊富なスタッフが、目的・テーマ・予算に合わせた最適な講師をご提案します。
講演会の終わりの挨拶(謝辞)の役割とは?

閉会時の挨拶や謝辞には、講演を終えるにあたり受け取った学びや感謝の気持ちを伝える意味があります。その概要と重要性、そして多くの人が知りたい“適切な伝え方”を確認しましょう。
終わりの挨拶は、講演全体を振り返りつつ感謝を伝える役割を担うため、講師や参加者の満足度を左右する重要な部分です。特に講師への労いの言葉や、参加者に向けた思いやりあるメッセージがあると、講演会の印象がさらに良くなります。多くの人は、謝辞をどう組み立てればよいか、どの程度の長さが適切かといった具体的な方法を知りたいと思うものです。講演会の終わりを気持ちよく締めくくるために、まずは謝辞の重要性を正しく理解しておきましょう。
謝辞の基本構成:必ず伝えるべき4つの要素

講演会の謝辞を考えるうえで大切なのは、「感謝」と「振り返り」を軸に構成することです。
押さえるべき4つの要素を意識することで、形式的にならず、心に残る挨拶になります。
謝辞に盛り込むべき内容は次の4つです。
①講師への感謝 ②講演内容への言及 ③参加者へのねぎらい ④今後への展望。
この流れを意識すると、全体の構成にまとまりが生まれ、聞き手に誠意が伝わりやすくなります。
講師がどのような思いで話してくれたのかを想像しながら言葉を選ぶと、より温かみのある表現になるでしょう。
最後に、次回への期待を添えることで、講演会の余韻を心地よく残せます。
1. 講師への感謝
講師が多忙のなか時間を割いて講演を行ってくれたことへのお礼は、最も重要な要素です。具体的な学びや印象に残った一言を交えて感謝を伝えると、定型文ではなく“あなた自身の言葉”として響きます。講師の専門性や熱意に敬意を込めて一言添えると、短い挨拶でも誠意が伝わりやすくなります。
2. 講演内容への言及と感想
講演の要点を簡潔にふれ、どのように役立つと感じたかを具体的に述べましょう。たとえば「本日の講演で学んだ視点を、今後の活動に活かしていきたい」といった表現です。講師の考えに共感し、それを広げていきたいという姿勢を見せることで、講師・参加者双方に好印象を残せます。
3. 参加者へのねぎらい
講師への感謝だけでなく、参加者への言葉も忘れずに。「お忙しいなかご参加いただきありがとうございました」「質疑応答へのご協力に感謝します」など、一言添えることで会全体に温かい雰囲気が生まれます。参加者が“自分も講演会を作る一員だ”と感じられるような言葉選びを意識しましょう。
4. 今後の期待や次回案内
謝辞の締めくくりでは、未来への前向きなメッセージを加えましょう。「次回も皆様とお会いできることを楽しみにしています」など、次のつながりを感じさせる一言があると、印象的な終わり方になります。学びを次にどう活かすかを共有することで、参加者や講師との関係をより深めることができます。
謝辞を述べるときに押さえたいマナーと注意点

講演会の締めくくりとして謝辞を述べる際は、言葉遣いやマナーが印象を左右します。せっかくの感謝の気持ちも、表現や立ち振る舞いを誤ると伝わりにくくなることがあります。ここでは、講演会の謝辞で失敗しないために知っておきたいマナーと注意点を解説します。
謝辞はフォーマルな場面で行われることが多いため、丁寧な敬語と自然な話し方のバランスを取ることが大切です。また、花束贈呈や記念品の進行、オンライン開催など、講演会の形式によって注意点も変わります。形式ばらず誠実に、そして状況に応じた柔軟な対応を心がけることで、聴き手の印象がぐっと良くなります。
敬語表現や言葉遣いのポイント
講師を呼ぶ際は、「先生」「氏」など、肩書きや立場に合わせた敬称を用いましょう。冒頭で「本日はご多忙のなか、貴重なお時間を頂戴し誠にありがとうございます」と伝えると、丁寧で好印象です。ただし、形式的すぎる敬語の乱用は逆効果。距離を感じさせない、温かみのある表現を心がけましょう。
また、話し方も重要です。声のトーンは少し明るめに、テンポはゆっくりと。早口や小声にならないよう注意し、相手に届く発声を意識します。特に「感謝」や「お礼」といったキーワードは、少し間を取って丁寧に伝えると印象に残ります。
花束贈呈など他の挨拶との連携
講演会の終盤では、謝辞と併せて花束や記念品を贈呈するケースもあります。その際は、渡す順番やタイミングを司会・運営スタッフと事前に確認しておくことが大切です。謝辞の途中で動作が重なると、感謝の流れが中断されてしまう可能性があります。
スムーズに進めるためには、「謝辞 → 贈呈 → 写真撮影 → 拍手」といった一連の流れを事前に共有しておきましょう。感謝の言葉と動作を自然に繋げることで、全体の印象が引き締まります。
オンライン開催の場合の進行上の配慮
オンライン講演会での謝辞は、リアル会場以上に“伝わり方”への工夫が必要です。画面越しでも感謝の気持ちが伝わるよう、「画面越しではありますが、本日も熱心にご参加いただきありがとうございました」といった表現を添えると効果的です。
また、通信環境や音声の確認はもちろん、万が一トラブルが起きた際の代替進行(司会が代読するなど)を準備しておくと安心です。話す際はカメラの位置を意識し、視線を合わせて話すことで、聴き手に誠実な印象を与えられます。オンラインでも、少しの気配りが大きな信頼につながります。
シーン別:講演会の謝辞例文集

講演会の謝辞は、開催形式(対面・オンライン)や規模(小規模・大規模)によって、伝え方や言葉の選び方が変わります。ここでは、よくあるシーン別にすぐ使える謝辞例文を紹介します。
形式や会場の雰囲気に合わせて、話す時間・内容のボリュームを調整しましょう。短い時間でも要点を押さえれば十分に感謝を伝えられます。以下の例文を参考にしながら、自分の言葉や状況に合わせてアレンジしてみてください。
対面開催:短めの謝辞例
本日は、お忙しいなかお集まりいただき誠にありがとうございます。講師の方には、限られた時間の中で非常にわかりやすく、かつ深いお話をしていただき、心より感謝申し上げます。ご参加の皆様にもご協力を賜り、スムーズに進行できましたことを重ねてお礼申し上げます。
対面開催では、講師と参加者双方の「距離の近さ」を意識して、表情や姿勢でも感謝を伝えましょう。
話す長さは1分以内が目安です。
オンライン開催:長めの謝辞例
オンラインという形式ではありましたが、皆様一人ひとりが熱心に耳を傾けてくださり、心より感謝申し上げます。通信環境の不安もある中、無事に講演を終えられたのは、皆様のご協力のおかげです。本日の学びを今後の業務や日常生活にぜひ活かしていただき、また次回のイベントでお会いできることを楽しみにしております。
オンラインでは、通信環境などの支援に対する感謝を一言添えると印象が良くなります。
声のトーンをやや明るめにし、画面越しでも伝わる笑顔を意識しましょう。
大規模イベントでの謝辞例
本日は、多数の皆様にご参加いただき、盛況のうちに講演会を終えることができました。講師の幅広いご見識と貴重なお話は、私たちに多くの学びと気づきを与えてくださいました。今後も皆様にとって有益な情報を共有できる場を継続的に提供できるよう、スタッフ一同努めてまいります。
大規模イベントでは「主催者としての総括」を意識しましょう。
感謝+展望(次回予告や継続的な取り組み)を盛り込むと締まりのある印象になります。
社内研修・セミナーでの謝辞例
本日はご多忙の中、社内研修にご参加いただきありがとうございました。講師の方から伺った具体的な事例や実践的なアドバイスは、私たちの業務にも直結する内容ばかりでした。今日の学びをチームで共有し、日々の仕事に活かしてまいります。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
社内研修では「実務への応用」「チームへの共有」などのフレーズを入れると現実的で好印象です。
ビジネス文書の要素を意識しながらも、温かみのある言葉でまとめましょう。
講演会を主催予定の方へ
謝辞の準備だけでなく、講師選定・テーマ相談・当日の運営まで、Hitonovaがサポートいたします。
ご希望の内容や予算に合わせて、最適な講師をご紹介します。
▶︎ 講師派遣のご相談はこちら
立場別:主催者・司会・生徒代表の講演会謝辞例文

講演会の謝辞は、誰が話すか(主催者・司会者・生徒代表)によって伝えるべき内容や言葉のトーンが変わります。それぞれの立場に合った言葉選びを意識することで、より真心が伝わる印象的な挨拶になります。
ここでは、各立場ごとの謝辞例文と、話す際に意識したいポイントをあわせて紹介します。自分がどの立場で話すのかを踏まえながら、状況に合わせてアレンジしてみてください。
主催者による謝辞例文
本日の講演会を無事に開催できましたのは、講師の方々のご協力、そして準備から当日の運営を支えてくださったスタッフの皆様、さらにはご参加くださった皆様のおかげです。
限られた時間の中で多くの学びを得ることができました。ここで得た知見を今後の活動にも生かしてまいります。
今後とも、皆様にとって有意義で魅力的な場を提供できるよう努めてまいりますので、どうぞご期待ください。
主催者としての謝辞では、講師・運営スタッフ・参加者の“三方向への感謝”を意識しましょう。
また、「今後の展望」や「継続的な取り組み」に触れることで、主催団体の信頼感が高まります。
司会者による謝辞例文
本日の講演を進行させていただきました司会の〇〇です。講師の先生、そしてご参加いただいた皆様のご協力により、講演を滞りなく終えることができました。限られた時間の中でも、皆様の温かいサポートとご理解のおかげで充実した時間となりました。また次回の講演会でも皆様にお会いできることを楽しみにしております。
司会者の謝辞は「中立的な立場」で進行を締めくくる役割があります。
講師や参加者への感謝を述べつつ、「スムーズに進行できたこと」を強調すると自然です。
長くなりすぎないよう、1分以内・3文程度が目安です。
生徒代表による謝辞例文
本日はお忙しい中、私たち生徒のために貴重なお話をしていただき、誠にありがとうございました。
講演を通して、将来の進路や生き方について多くの気づきを得ることができました。
今日の学びを日々の学校生活に活かし、自分の目標に向かって努力していきたいと思います。
改めて、講師の先生方や講演を準備してくださった皆様に心より感謝申し上げます。
生徒代表の謝辞は「素直さ」と「学びの姿勢」を意識してまとめましょう。
難しい言葉よりも、自分の言葉で感じたことを短く伝えるほうが印象に残ります。
最後に「成長への意欲」を添えると、講師や聴衆の心に響きます。
謝辞で意識したい話し方のポイント
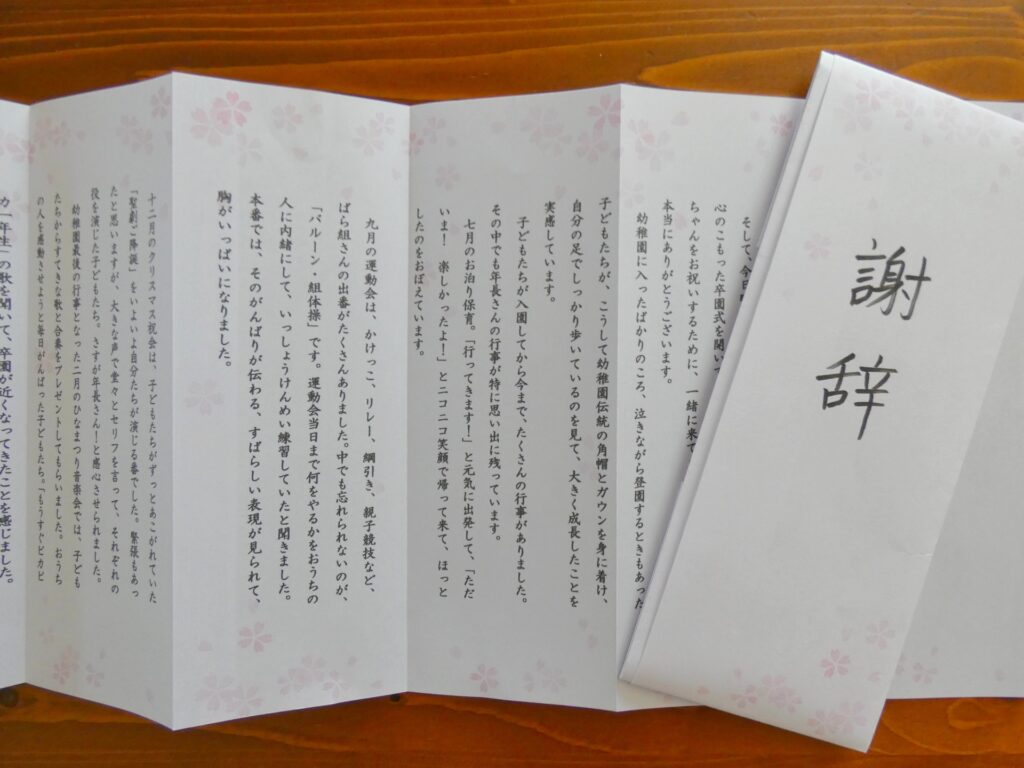
講演会の謝辞は、内容と同じくらい「話し方」も大切です。どれだけ良い文章でも、伝え方ひとつで印象が変わります。ここでは、講演会で謝辞や終わりの挨拶を行う際に意識したい「話し方の基本」や「緊張を和らげるコツ」を紹介します。
謝辞を述べるときは、台本をそのまま読むよりも、相手の顔を見ながら自然に語る意識が重要です。声の大きさ・スピード・視線の配り方を少し工夫するだけで、誠実で温かい印象を与えられます。本番で落ち着いて話せるように、以下のポイントを押さえて準備しておきましょう。
緊張対策:あがらないためのコツ
人前で話すときに緊張するのは自然なことです。
大切なのは「完全に緊張をなくそう」とせず、緊張をコントロールする準備をすること。
・深呼吸と軽いストレッチ:話す直前に呼吸を整えると、心拍数と声が安定します。
・事前リハーサル:声に出して数回練習することで、言葉の詰まりや不安を減らせます。
・メモは要点だけ:全文を読むより、キーワードを箇条書きにする方が自然な視線移動ができます。
緊張しても、最初の一文を落ち着いて言えればその後は流れに乗りやすくなります。
自分の言葉で伝えるつもりで話せば、少しのミスも自然に聞こえます。
声の大きさ・話す速度・視線の配り方
聞き取りやすさは謝辞の印象を大きく左右します。
小声や早口は内容が伝わりにくくなるため、少し大きめ・ゆっくりめを意識しましょう。
・声は「後ろの席にも届く」イメージで。
・一文ごとに短く区切り、落ち着いて発声する。
・視線は特定の人に偏らず、会場全体をゆっくり見渡すように。
オンライン開催の場合は、画面上のカメラを見ることで「相手の目を見る」代わりになります。
目線を下げすぎず、少し笑顔を添えると声にも明るさが出ます。
簡潔さと丁寧さの両立
謝辞は長ければ良いわけではありません。
むしろ、短くても丁寧な言葉で感謝を伝える方が印象に残ります。
・感謝 → 講演内容への触れ → 今後への言葉、の3ステップが理想的。
・敬語は「過剰に堅苦しくならない」程度に自然な表現で。
・話す時間はおおむね1〜2分を目安に。
冗長にならないよう要点を絞りつつ、「ありがとうございました」を心を込めて言うことが何より大切です。
簡潔で誠実な話し方こそ、講師や参加者に良い印象を残す謝辞になります。
まとめ・総括:講演会の謝辞で印象に残る締めくくりを
講演会の終わりの挨拶や謝辞は、講師・参加者の双方に感謝を伝えるだけでなく、イベント全体の印象を決定づける重要な場面です。本記事で紹介したように、感謝・内容への言及・参加者へのねぎらい・次への展望といった基本構成を押さえ、丁寧な言葉選びを意識することがポイントです。
適切な謝辞は、講師や参加者に「この講演会に参加してよかった」と感じてもらうきっかけになります。単なる形式的な挨拶ではなく、心のこもったメッセージとして伝えることで、次回のイベントや研修への期待感を高めることもできます。
また、あらかじめ台本を準備し、声のトーンや話す速度を意識してリハーサルしておくことで、当日の進行もスムーズになります。謝辞の一言が講演全体を締めくくる“ラストメッセージ”となることを意識し、主催者としての信頼と誠意をしっかりと伝えましょう。
講演会のご担当者さまへ
謝辞や進行だけでなく、講師選びやプログラム構成にお悩みではありませんか?
Hitonova では、講演テーマや目的に合わせた講師をご提案し、講演会の企画・運営をトータルでサポートしています。
▶︎ 人気講師を探す
▶︎ 講演会主催のご相談はこちら
Contact お問い合わせ
講師選びでお悩みの方には、目的・ご予算に合った講師をご提案します。
気になる講師のスケジュールや講演料についても、お気軽にお問い合わせください。
5営業日経過しても返信がない場合は、
恐れ入りますが電話かkouen@scg-inc.jpまでメールでお問い合わせください。

