Special 講演会アンケートを成功させるには?目的から質問例、作成のポイントまで徹底解説
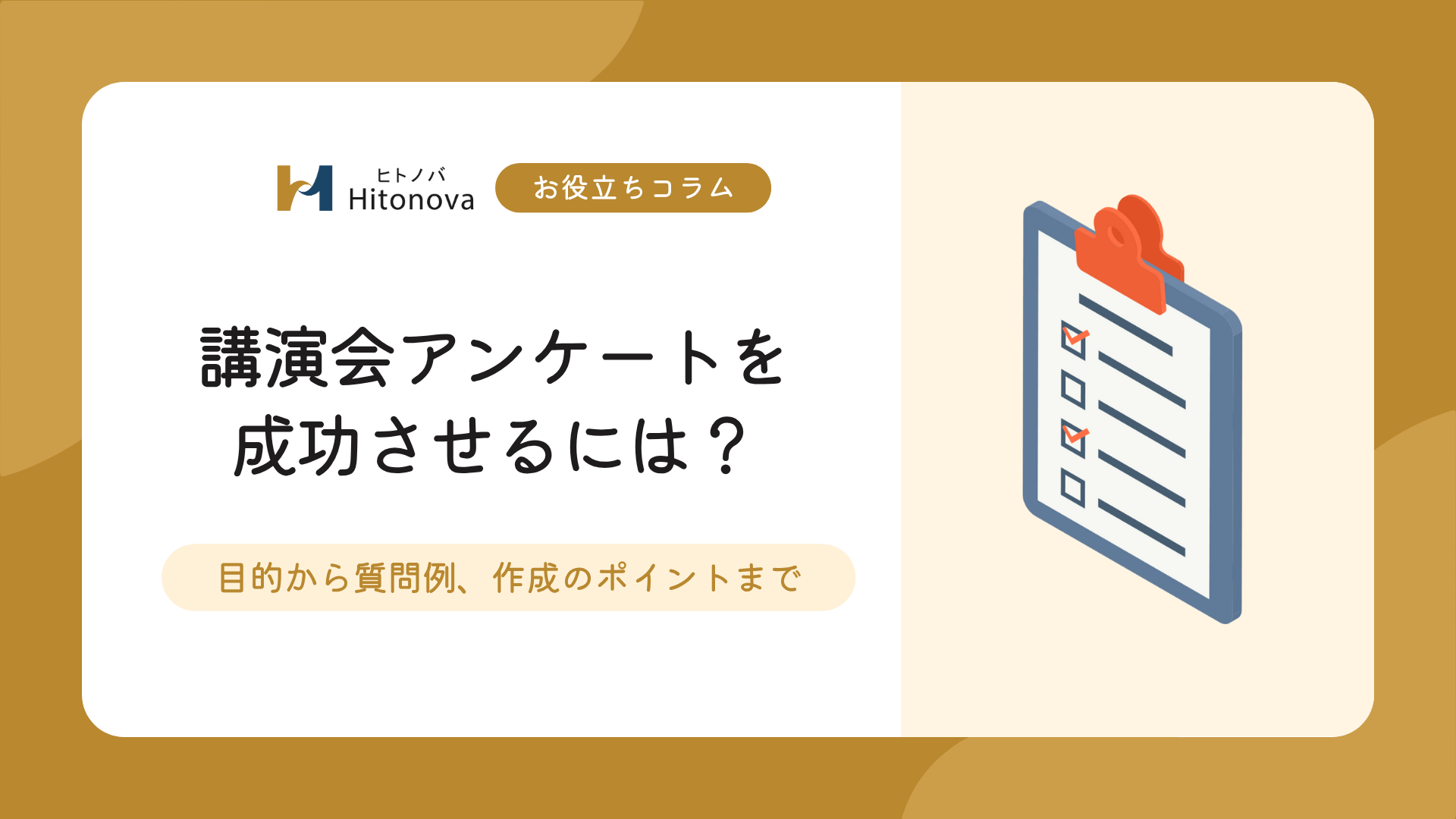
講演会をより良いものにするためには、参加者からのフィードバックが欠かせません。講演会アンケートを実施することで、参加者の満足度や改善点を把握し、次回以降の講演に活かすことができます。本記事では、講演会アンケートの目的や質問例、作成時の重要ポイントについて詳しく解説。効果的なアンケートの作成と運用を目指す方は、ぜひご一読ください。
アンケートの声からわかる
講演会の運営をより良くするためのヒントは、「アンケートの声」にあります。
Hitonovaでは、講演企画をサポートし、アンケート結果の活用や運営改善もお手伝いしています。
次の講演会をもっと良くしたい方は、まずはお気軽にご相談ください。
👉 お問い合わせフォームはこちら
講演会アンケートを実施する目的

講演会アンケートはただの感想集めでなく、具体的な改善や運営方針の最適化に直結する重要な材料です。ここでは主な目的を確認しましょう。
講演会の品質向上・改善を図る
参加者からのフィードバックは、講演全体の構成や進行方法を見直すための貴重なヒントになります。
プレゼンテーションの流れ、時間配分、内容の難易度など、主催者自身では気づきにくい課題を明らかにできるのがアンケートの大きな強みです。
得られた結果をもとにスライド構成や講師の話し方を改善すれば、講演の完成度と参加者満足度の双方を高めることができます。
参加者のニーズを把握する
一見適切に見える講演内容でも、実際の参加者が「もっと知りたかったこと」とズレている場合があります。
アンケートで関心のあるテーマや今後取り上げてほしい分野を尋ねることで、次回企画に反映しやすくなります。
参加者のニーズを的確に捉えることは、リピート参加の増加やファン層の形成にもつながり、長期的な講演会運営の成功を支える要素となります。
参加者情報の収集とフォローアップ
アンケートは、単に意見を集めるだけでなく、継続的な関係構築のための接点にもなります。
参加者の属性や関心領域、課題を把握しておくことで、講演後にフォローアップメールを送ったり、次回イベントの案内を届けたりといったコミュニケーション施策が可能になります。
参加者一人ひとりとの信頼関係を築くことは、次回の集客や新規企画の告知にも効果的です。
アンケート作成前に押さえておきたい事前準備

講演会アンケートの設問を考える前に、まずは目的と導入文を明確にしておくことが成功の第一歩です。
目的が曖昧なまま設問を作ると、質問の意図が散漫になり、参加者が答えにくいアンケートになってしまいます。
「なぜアンケートを実施するのか」「どんな情報を得たいのか」「どのように活用するのか」を最初に整理しておくことで、回答者にとってもわかりやすく、効果的なアンケートを設計できます。
アンケートの目的とゴールを設定する
アンケートを通じて何を把握し、どんな改善につなげたいのかを具体的に定義することが大切です。
たとえば「講演内容の満足度を数値化する」「今後の講演テーマへの関心を把握する」「フォローアップ用の連絡先を収集する」など、ゴールを明確にすれば質問設計の方向性が定まります。
結果として、質問が重複したり無駄に長くなることを防ぎ、参加者が無理なく回答できる構成に仕上げられます。目的が明確なアンケートは、回収率・回答精度ともに高まり、次回以降の改善にも直結します。
必要な導入文・説明文の作成
アンケートの導入文は、回答者の協力を得るための「入口」です。
冒頭でアンケートの目的や活用方法を簡潔に伝えることで、回答への理解と納得を得やすくなります。
たとえば「今後の講演運営の改善に活かすためにご意見をお聞かせください」など、回答の意義を具体的に説明しましょう。
また、個人情報の取り扱いや使用目的を明記することで、安心感と信頼感を高め、回答意欲を引き出す効果もあります。
講演会アンケートに必須の質問項目とは
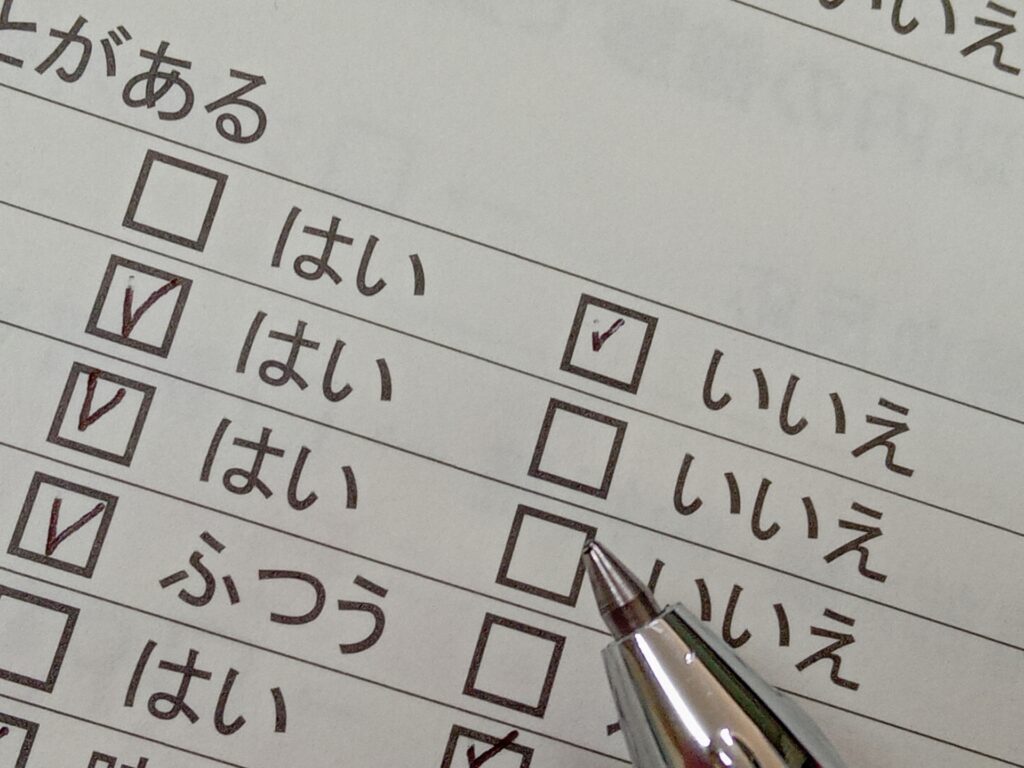
効果的な講演会アンケートを作成するには、聞くべき質問項目を明確に整理することが不可欠です。
限られた質問数でも、要点を押さえれば十分に有益なデータを得られます。
質問数が多すぎると回答率が下がり、少なすぎると必要な情報を取りこぼす恐れがあります。
重要なのは、「目的に合った設問を厳選し、バランスよく情報を収集すること」です。
個人情報・満足度評価・理解度・今後の関心など、基本項目を中心に設計していきましょう。
基本情報:氏名、連絡先、所属など
講演会後のフォローアップや参加者の属性把握には、最小限の個人情報の収集が欠かせません。
氏名・所属・連絡先を把握しておくことで、今後のイベント案内や追加資料の送付に活用できます。
ただし、プライバシー保護の観点から、回答者が安心して記入できる範囲にとどめることが大切です。
必須項目と任意項目を分けることで、回答率の低下を防ぐ効果もあります。
講演会内容への満足度
講演の満足度を数値で評価してもらうことで、講演の効果や評価を定量的に把握できます。
5段階評価や10点満点など、誰でも直感的に答えられる形式が理想です。
加えて「特によかった点」「改善を望む点」を自由記述で尋ねると、より深い洞察が得られます。
満足度の高い要素は今後も継続し、低評価だった要素は講師・構成・時間配分など具体的に改善していきましょう。
理解度・改善点の評価
参加者が講演内容をどれだけ理解できたかを把握することは、次回の内容改善に直結します。
「特に印象に残った部分」「もう少し説明してほしかった内容」などを尋ねると、
講師や運営が見落としがちな改善ポイントを発見できます。
受講者がつまずいた箇所を分析することで、講演会の構成・資料・説明方法の精度を高めることができます。
今後の講演テーマへの関心度
次回以降の企画を成功させるには、参加者が関心を持っているテーマを把握することが重要です。
アンケートで「次に聞きたいテーマ」「関心のある分野」を選択肢+自由回答形式で聞くと、
今後の企画立案に役立つデータを効率的に収集できます。
意外なリクエストや新しいニーズが見つかることもあり、リピート参加や継続的な関係構築にもつながります。
アンケート設問設計のポイント

講演会アンケートの成果は、設問設計の巧拙に大きく左右されます。
質問の作り方ひとつで、回答率や回答の質が大きく変わるため、設計段階での工夫が不可欠です。
選択式のシンプルな質問だけでなく、自由回答欄を適度に取り入れることで、定量データ(数値)と定性データ(意見)の両面から参加者の声を収集できます。
さらに、回答者が最後まで集中して回答できるよう、質問の順序・分量・表現の明確さにも注意を払いましょう。
答えやすい選択式と自由回答式のバランス
数値評価や選択式の設問は、回答が手軽で集計もしやすいというメリットがあります。
一方で自由回答欄は、参加者の生の声を直接拾うことができ、具体的な改善点や新しいアイデアを得るのに有効です。
両者をうまく組み合わせ、全体の設問ボリュームを最適化することで、回答者の負担を軽減しつつ、より質の高いデータを集めることができます。
重要項目は先に提示する
回答者はアンケートの前半で最も集中力が高く、後半に進むほど回答精度が下がる傾向があります。
そのため、最も重要な設問を冒頭に配置することが効果的です。
「今回の講演で最も印象に残った点は?」「講演内容の満足度を教えてください」といった核心部分を最初に置くと、より正確で価値の高い回答を得やすくなります。
限られた回答時間を有効に活かす工夫が、アンケート全体の成果を左右します。
参加者の潜在的意見を引き出す工夫
アンケートでは、主催者が想定していなかった意見や新しいアイデアが出てくることがあります。
自由記述欄を一部に設け、「ご自由にご意見をお聞かせください」など気軽に書ける雰囲気を作ることが重要です。
回答欄に十分なスペースを確保するだけでも、参加者が自分の考えを整理しやすくなり、講演の質を高めるヒントが得られることがあります。
オンライン・オフラインそれぞれへの配慮
講演会の形式に応じて、アンケート設計も最適化しましょう。
オフライン(紙)では書きやすさと見やすいレイアウトを、オンラインではスマートフォン対応のUIを重視します。
特にオンラインでは、質問数を減らし操作ステップを最小限にすることで、回答離脱を防げます。
回収率と回答者満足度の両立を意識した設計が、アンケート成功の鍵です。
回答率を上げるための工夫

せっかく丁寧にアンケートを作成しても、回答率(回収率)が低ければ十分な効果は得られません。
ここでは、参加者が積極的に回答したくなる仕組みづくりと、講演会アンケートの回答率を高める実践的なコツを紹介します。
回答率を左右するのは、設問のわかりやすさだけではありません。
回答のしやすさ、回答までの導線の短さ、そして参加者が「答えるメリット」を感じられる工夫が重要です。
複数の要素を組み合わせ、参加者がストレスなく意見を伝えられる環境設計を目指しましょう。
アンケート実施のタイミングと回収方法
アンケートは、参加者の記憶が新鮮なタイミングで実施するのが最も効果的です。
講演会の終了直後や休憩時間中など、感想をリアルタイムで書ける状況を作ると、具体的で有益な回答を得やすくなります。
オンライン講演会では、イベント終了後にメールやQRコードでフォームURLを配信するとスムーズです。
回収手段を複数用意し、「その場で回答できる」仕組みを導入すると、回収率アップにつながります。
回答者の負担を減らす設問数とレイアウト
長すぎるアンケートは、途中離脱を招く大きな原因です。
質問数は目的に合わせて最小限に絞り、全体で3〜10問程度が理想的。
設問の順序を整理し、レイアウトを見やすく直感的に操作できるように設計することで、最後まで回答してもらいやすくなります。
視覚的な区切りやプログレスバーを設けるなど、回答ストレスを軽減するUI設計も有効です。
インセンティブの検討
参加者にとって、回答する動機を明確にすることは非常に重要です。
例えば、抽選で景品を贈る・次回イベントの割引クーポンを提供する・講演資料を特典配布するなど、具体的なメリットを設定しましょう。
ただし、インセンティブを重視しすぎてアンケートの目的がブレないよう注意が必要です。
「意見を反映する」「改善に活かす」姿勢を明示しつつ、感謝の気持ちを添えることが理想的です。
丁寧な依頼文とフォローアップ
アンケートの依頼文は、単なる「お願い」ではなく、参加者との信頼を築くコミュニケーションの一部です。
依頼時には、「このアンケート結果をどのように活用するか」を明確に伝えることで、回答者の納得感が高まります。
回答後には感謝のメッセージや結果共有メールを送ることで、次回以降の協力にもつながります。
リマインドメールのタイミングも重要で、イベント後1〜3日以内が最も効果的です。
講演会アンケートのテンプレート例
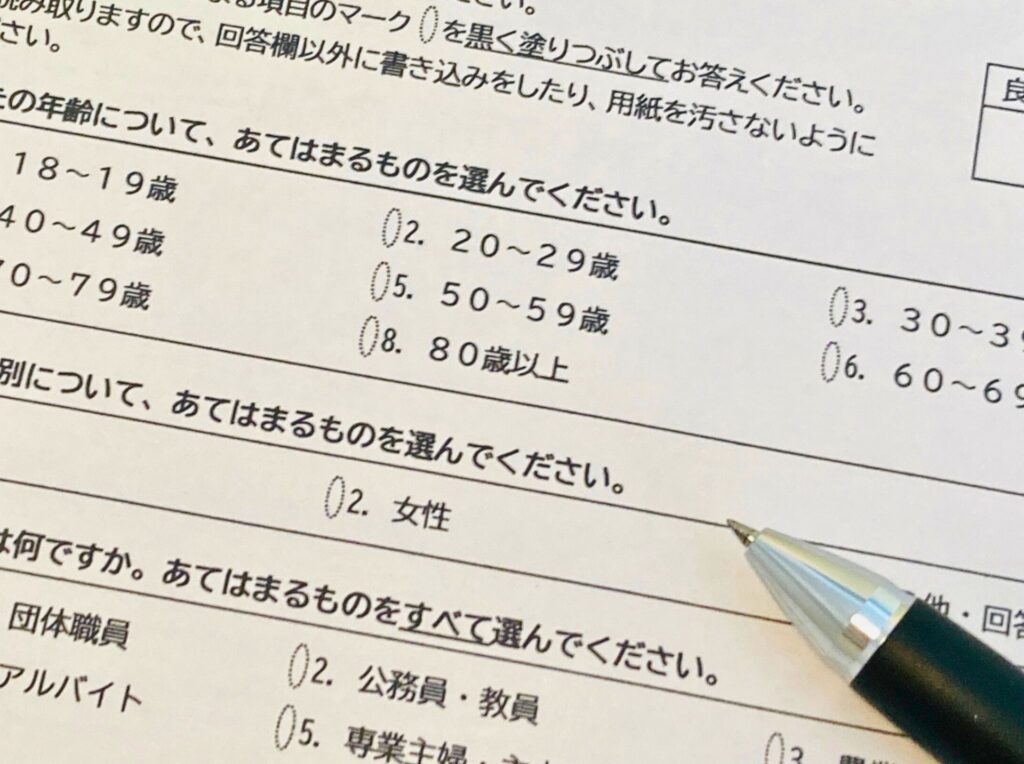
ここでは、実際に使える講演会アンケートのテンプレート例をもとに、作成時のポイントをわかりやすく解説します。
テンプレートを活用することで、設問の抜け漏れやレイアウトの煩雑化を防ぎ、短時間で効果的なアンケートフォームを作成できます。
紙とオンラインの両方に対応した形式を用意しておくと、参加者の環境や開催形式に合わせて柔軟に対応できるのが理想です。
ただし、テンプレートはあくまで「たたき台」です。実際の講演会の目的・対象層・講師の特徴に合わせて、言葉や質問内容を微調整しましょう。
紙アンケートのレイアウト例
紙で実施する場合は、見やすさと書きやすさを最優先に設計します。
質問項目は「基本情報」「内容への評価」「自由意見」など、大きなまとまりごとに区分して配置しましょう。
回答欄には十分なスペースを確保し、文字サイズは小さすぎないよう配慮します。
また、各セクションの冒頭に見出しや簡単な説明を添えることで、回答者が自分のペースで迷わず記入できる構成になります。
デザインはできるだけシンプルにし、余白を活かした読みやすいレイアウトを意識すると良いでしょう。
オンラインフォームの設計例
オンラインアンケートでは、操作のしやすさ(UI/UX)が回答率を左右します。
ページ遷移はなるべく少なくし、1画面で完結できる構成にするのがポイントです。
特にスマートフォンからの回答を想定し、タップしやすい選択式ボタンやチェックボックスを中心に設計しましょう。
自由記述欄を設ける場合は、文字数制限を厳しくしすぎないように注意します。
「自由にご意見をお聞かせください」などのポジティブな文言を添えると記入率が向上します。
また、送信ボタンの位置や完了メッセージも明確にしておくことで、最後までストレスなく回答を終えられます。
アンケート結果の集計・分析方法

講演会アンケートを実施したら、次に重要なのが「結果の活用」です。
せっかく集めた回答も、ただ目を通すだけでは意味がありません。
定量データ(数値)と定性データ(意見)をバランスよく分析し、改善や次回企画に結びつけることが成功の鍵です。
分析の目的を明確にしたうえで、数値の傾向・参加者の感情・改善要望の3つの観点から整理しましょう。
さらに、スタッフや講師との共有を行うことで、より具体的で効果的なアクションプランを導き出せます。
最近では、ExcelやGoogleフォームの自動集計機能、テキストマイニングツールなどを活用して、効率的かつ視覚的に結果を分析する方法も増えています。
定量データの集計とグラフ化
満足度・理解度・再参加意向などの数値評価項目は、グラフ化することで全体傾向を直感的に把握できます。
棒グラフ・円グラフ・レーダーチャートなどを活用し、平均値や中央値だけでなく、回答の分布(ばらつき)にも注目するのがポイントです。
たとえば、「満足度が高い層」と「やや不満層」を比較すれば、改善すべき具体的な要素が見えてきます。
シンプルなグラフとコメント抜粋を並べて提示することで、スタッフ全体が理解しやすく、改善会議などでも共有しやすい資料になります。
自由回答のテキストマイニング
自由記述欄には、最も具体的で実践的なヒントが隠れています。
回答が多い場合は、単純な読み込みでは傾向を把握しづらいため、
「頻出キーワードの抽出」や「ポジティブ/ネガティブ分析」といったテキストマイニング手法を活用しましょう。
例えば、「印象に残った点」「改善してほしい点」といったテーマ別に分類すると、共通の意見や新しいアイデアが浮かび上がります。
ツールを使わずに整理する場合でも、Excelの「検索・置換」機能でキーワード出現回数を数えるだけでも、傾向分析の第一歩になります。
セグメント別の比較と傾向分析
より深い分析を行うには、回答を属性(年齢層・職種・部署・参加形態など)別にセグメント化して比較します。
これにより、「学生と社会人」「管理職と一般社員」など、立場による感じ方やニーズの違いを明確にできます。
特定の層がどのテーマに強い関心を持っているかを把握すれば、次回の講演テーマや告知戦略に反映可能です。
こうしたデータドリブンな分析を行うことで、講演会の満足度向上とリピート参加率の改善を同時に実現できます。
アンケート結果の共有とフィードバック

アンケート結果を最大限に活かすためには、関係者への共有と参加者へのフィードバックを丁寧に行うことが欠かせません。
せっかく収集したデータも、分析結果を保管するだけでは意味がなく、行動に移して初めて価値を発揮します。
結果をわかりやすく可視化し、迅速に共有することで、改善策の検討や次回講演の企画がスムーズに進行します。
さらに、アンケート回答者への丁寧なフォローアップを行うことで、講演会全体の信頼性・ブランド価値・リピート率の向上につながります。
講演者やスタッフとの情報共有
まずは、アンケートで得たデータを講師や運営チームと共有しましょう。
良かった点や改善点を客観的に分析し、次回の運営や講演内容に反映させることが重要です。
意見が分かれる場面でも、具体的な数値や参加者の声という“根拠”があれば、建設的な話し合いが可能になります。
定例の振り返りミーティングや報告書を作成し、成功事例・改善点・提案事項を整理して共有することで、継続的な質の向上を実現できるでしょう。
また、共有の際は「定量データ」「自由回答」「講師評価」などのカテゴリ別にまとめると、議論の方向性が明確になります。
参加者へのフォローアップメール
アンケートに協力してくれた参加者には、感謝と結果の共有を兼ねたフォローアップメールを送ることがおすすめです。
「皆様のご意見をもとに次回はこのような改善を行います」と伝えることで、参加者は自分の声が反映されていると感じ、主催者への信頼感が強まります。
また、メール内で次回の講演予定や関連コンテンツ(講演資料・アーカイブ動画・関連コラムなど)を紹介すると、自然な形で次の参加促進につなげることができます。
簡潔で温かみのある文面を心がけ、「ご回答ありがとうございました」「今後の改善に活かしてまいります」といったポジティブなトーンを維持することが大切です。
参加者が本当に求めているテーマ
アンケートを通じて見えてくる「参加者が本当に求めている講演テーマ」。
SHOEI講演会事業部では、企業・教育機関・自治体などの目的に合わせて、最適な講師をご提案しています。
講演企画やテーマ選定でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
👉 講師検索・ご相談はこちら
アンケート結果を次回の講演会運営に活かす方法

アンケートは「回収して終わり」ではなく、「次につなげてこそ価値がある」ものです。
参加者の声を分析・整理し、次回の講演会の企画・運営・集客改善に反映することで、イベント全体の質を大きく高めることができます。
ここでは、実際にアンケート結果を講演会運営に活かすための3つのステップを紹介します。
改善ポイントを優先順位づけする
アンケートから得られた改善点をすべて一度に対応しようとすると、リソースが分散して効果が薄れてしまいます。
まずは、満足度が低かった項目や、複数の参加者が指摘した共通の課題に優先的に取り組みましょう。
特に注目すべきは次の3点です
・複数の人が同じ不満・要望を挙げている項目
・満足度スコアが平均を下回った質問
・改善すれば大きな満足度向上につながる部分(例:時間配分・音響・資料配布など)
優先順位を明確にすることで、限られた時間や予算の中でも具体的で実行可能な改善策を立てやすくなります。
講師・運営スタッフと共有してPDCAを回す
アンケート結果は、講師・司会・スタッフなど全関係者で共有し、振り返りを行うことが重要です。
数値やコメントをもとに「なぜこの評価になったのか」を分析すれば、より効果的な改善策が導き出せます。
特に講師からのフィードバックは、運営サイドが気づかない講演構成・時間配分・参加者反応などの観点を補ってくれます。
共有会では、「何を継続し」「何を改善するか」を明文化し、次回に向けたPDCAサイクルを確実に回す仕組みを作りましょう。
これを継続することで、講演会の完成度が毎回向上していきます。
ポジティブな声を広報・集客に活用する
アンケートには、改善点だけでなく次回講演のPRに使えるポジティブな意見も多く含まれています。
たとえば、以下のような方法で活用できます
・「参加者の声」として公式サイトやSNS、チラシに掲載
・満足度スコアをグラフィック化して実績として紹介
・講師プロフィールページや次回告知ページに引用
こうした実際の参加者の声=信頼性の高い口コミは、次回講演の集客効果を高める強力な要素になります。
また、ポジティブな意見を講師や関係者に共有することで、モチベーション維持にもつながり、イベント全体の向上サイクルを生み出せます。
アンケート作成時の注意点

講演会アンケートの作成では、個人情報の扱いと回答者への配慮が何より重要です。
とくに、氏名や連絡先などを収集する場合は、利用目的・プライバシー保護・質問設計の3点を意識しなければなりません。
法令で定められた個人情報保護の基準を遵守しつつ、回答者の負担を最小限に抑える工夫をすることで、信頼性の高いアンケートと高い回収率の両立が可能になります。
また、設問の表現や順序にも注意し、誰が読んでもわかりやすい・答えやすい構成を心がけましょう。
プライバシー保護と個人情報管理
講演会のアンケートでは、参加者の氏名・所属・メールアドレスなど、個人が特定される情報を扱うケースが多くあります。
そのため、データの取り扱い方針をアンケート冒頭や同意文で明示しておくことが必須です。
たとえば、以下のような説明を添えると安心感が生まれます。
「ご回答いただいた内容は、講演会運営の改善および今後のご案内にのみ使用いたします。個人を特定できる形で外部に公開することはありません。」
また、データは安全な環境(パスワード保護・アクセス制限・暗号化)で保管し、利用目的が達成された後は速やかに削除または匿名化しましょう。
こうした取り組みが、参加者からの信頼獲得とリピート参加の基盤になります。
設問が多すぎないか再確認
アンケート作成では、「もっと詳しく知りたい」と思うあまり設問数が増えがちです。
しかし、質問が多すぎると回答離脱率が上がり、精度の高いデータが得られなくなる可能性があります。
目的を明確にしたうえで
絶対に必要な質問
あれば望ましい質問
を分類し、必要最低限の設問に絞ることが大切です。
特にオンラインフォームでは、進行バー(残りの質問数)を表示するなど、回答者の心理的負担を軽減する工夫も効果的です。
回答しやすい言葉遣いか
専門用語や抽象的な表現は、回答者に誤解や負担を与える原因になります。
「わかりやすく・短く・一文一義」を意識して、誰でもすぐ理解できる設問文に整えましょう。
たとえば
❌「講師のプレゼンテーションにおける情報伝達の効果性をどう感じましたか?」
✅「講師の話はわかりやすかったですか?」
のように言い換えるだけで、回答しやすさが格段に向上します。
特にスマートフォン回答が増えている昨今では、短文でスクロールしやすいUIを意識することも重要です。
質問の目的を明確に示す
参加者にとって「なぜこの質問が必要なのか」がわからないと、本音の回答を引き出しにくくなります。
質問の前後に一言添えるだけでも、協力意識が高まります。
例
「今後のテーマ設定の参考にさせていただくために、お聞かせください。」
「より良い運営を目指すため、率直なご意見をお願いします。」
このように質問の意図を明確にすることで、回答者が安心して意見を伝えやすくなり、結果として質の高い回答データが集まります。
オンライン講演会でのアンケート活用ポイント

オンライン講演会では、ツールや配信環境を活かしたアンケート設計が成果を大きく左右します。
リアル会場と違い、参加者が画面越しで関わるため、アクセスのしやすさ・回答のしやすさ・UX設計が特に重要です。
オンライン形式の最大の利点は、講演中や終了直後にリアルタイムでアンケートを実施できること。
ZoomやTeams、YouTube配信などでは、フォームURLやQRコードを提示するだけで、短時間で多くの意見を集められます。
一方で、通信環境やデバイスの違いによって回答しづらくなることもあるため、「誰でもすぐにアクセスできる導線設計」を徹底しましょう。
ツール選定とフォーム作成時の注意
オンライン講演会では、使用するツールに応じたアンケート連携の最適化が欠かせません。
ZoomウェビナーやGoogleフォーム、Microsoft Formsなど、各ツールには独自の特徴があります。
外部フォームを利用する場合は
・講演会の視聴環境(PC/スマホ)で操作しやすいか
・画面共有中でもアクセスしやすいリンク配置になっているか
・アクセス集中時にも動作が安定しているか
を確認しておきましょう。
また、URLリンクだけでなく、講演スライドやチャット欄に固定表示することで、回答率を高められます。
参加者が一度の操作で回答を完了できるよう、入力項目を最小限に設計することもポイントです。
ライブ配信中のQRコード活用
ライブ配信やオンラインイベントでは、QRコードを使ったアンケート誘導が非常に効果的です。
プレゼンテーション画面やスライドの最後にQRコードを表示すれば、スマートフォンからすぐに回答できます。
特にZoomやTeamsなどの配信では
・スライド内に高コントラスト(黒×白)で大きめのQRコードを配置
・一時停止して「この時間でご回答ください」とアナウンス
・終了画面やお礼メールにもQRコード・URLを再掲
といった工夫を加えると、リアルタイムで多くの回答を集めることが可能です。
コメント欄での質問やリアクションよりも参加ハードルが低く、幅広い層からの意見収集につながります。
参加体験を高めるための工夫
オンラインでは対面以上に「参加者の一体感」が生まれにくいため、アンケートもコミュニケーションの延長線として位置づけましょう。
たとえば
・「ご意見を次回テーマ選定に活かします」と明示して回答意欲を高める
・回答後にサンクスページや特典リンクを設ける
・後日「ご回答ありがとうございました」メールでフォローする
といった工夫により、アンケートを通じて次の参加や信頼関係づくりにつなげることができます。
まとめ
講演会アンケートは、講演内容の質向上や参加者とのコミュニケーション強化に欠かせないツールです。事前準備から設問設計、結果の分析・共有まで一連の流れをしっかりと押さえ、より充実した講演会運営を目指しましょう。
アンケートを活用すれば、講演会の改善だけでなく、主催者と参加者との長期的な関係づくりにも役立ちます。講演内容の質や運営方法の見直し、次回のテーマ案の参考など、多角的な視点から充実したイベントにつなげていくことができるでしょう。重要なのは、回収したデータをきちんと分析し、具体的なアクションに結びつけることです。継続的にブラッシュアップを重ね、参加者が満足する講演会を形作っていきましょう。
参加者が本当に求めているテーマ
講演会の満足度を高めるには、アンケート設計と同じくらい講師選びも大切です。
SHOEI講演会事業部では、テーマ・対象・目的に合わせて全国の人気講師をご紹介しています。
「アンケートで見えた課題に合う講師を探したい」という方は、下記ページをご覧ください。
👉 人気講師一覧を見る
Contact お問い合わせ
講師選びでお悩みの方には、目的・ご予算に合った講師をご提案します。
気になる講師のスケジュールや講演料についても、お気軽にお問い合わせください。
5営業日経過しても返信がない場合は、
恐れ入りますが電話かkouen@scg-inc.jpまでメールでお問い合わせください。

