Special 講師依頼文の書き方完全ガイド|必須項目と送付方法を網羅
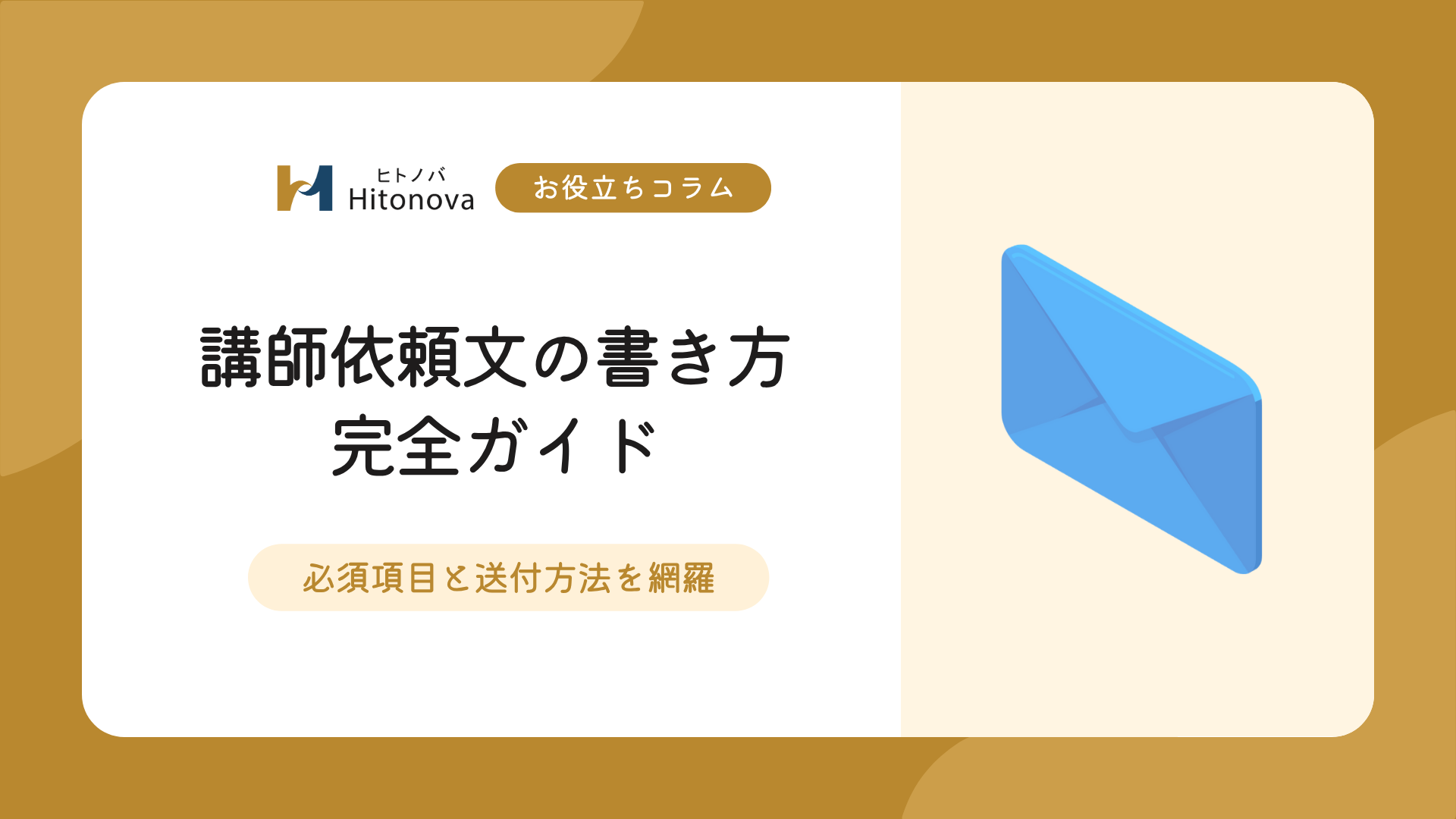
講師に正式に依頼する際、適切な内容や形式を踏まえた文書を作成することは非常に重要です。特にイベントやセミナーの質を高め、多くの参加者の満足度を得るためには、講師側の負担を減らしながら必要な情報をしっかり伝えなければなりません。本記事では、頼りになる講師依頼文の作り方を初心者でもわかりやすく解説します。
イベントの3〜6ヶ月前に講師へ声をかけると、スケジュールの調整や講演内容の打ち合わせがスムーズに進みます。複数の講師に同時依頼をしないことだけでなく、連絡先や謝礼の内容など必要事項を正確に伝えることもポイントです。スムーズにやりとりが進めば、当日の進行や講演準備も安心して進められるでしょう。
本記事では、依頼前に押さえておきたいポイントから具体的な必須項目、送付方法やトラブル時の対処法までを徹底的に紹介します。ぜひ記事を参考に、講師との信頼関係を築きながら満足度の高いイベントを実現してください。
この記事でわかること
・初めてでも失敗しない「講師依頼文」の基本構成と書き方
・必ず盛り込むべき必須項目
・メール・郵送・オンラインフォームなど、送付手段別の注意点
・トラブルを防ぐためのポイントと、依頼が断られた時の対応法
・外部の講師派遣サービスを利用する際のメリットと注意点
講師依頼文とは?その役割と重要性

最適な講師を招くための第一歩として、明確かつ正式に依頼の意思を伝える必要があります。ここでは、講師依頼文の基本的な役割と重要性を確認していきましょう。
講師依頼文は、主催者の意図や計画を講師に正確に伝えるための公式文書です。例えば、イベントの目的や対象者の属性、期待する講演の内容などをきちんと整理し、講師の立場に立って書くことが求められます。書き方次第で、講師との初期段階の信頼関係が大きく左右されるため、簡潔かつ具体的な表現を心がけることが重要です。
依頼前に確認しておきたい3つのポイント

依頼前には、事前準備として押さえておくべき事項があります。以下の3つのポイントを徹底的に確認してください。
講師依頼文を作成するにあたり、ただ闇雲に依頼内容を伝えるだけでは不十分です。何を伝えるべきか、どのような背景や意図があるかをしっかり固めておくことが大切です。以下の3項目を押さえると、依頼後の行き違いや余計な手戻りを減らすことにつながります。
①講演の目的・テーマを明確にする
最初に大切なのは、講演の目的やテーマを主催者側で明確にすることです。どのような背景があって、どんな成果を得たいのか、といった内容があやふやなまま依頼すると、講師自身も準備が難しくなります。講師が納得しやすいように、このイベントでどのような学びやメリットを期待しているのかを簡潔にまとめておきましょう。
②謝礼・予算・スケジュールを事前調整する
講演を依頼するうえでトラブルの原因になりやすいのが謝礼や予算です。交通費や宿泊費も含めて、支払い方法や金額をきちんと明記し、講師が納得していただける条件を提示することが重要となります。さらに、十分な期間を確保できるよう、理想的には3〜6ヶ月前に連絡し、追加の打ち合わせがスムーズに進むよう準備しておきましょう。
③複数の講師に同時依頼をしない
複数の講師に同時に依頼すると、スケジュールの重複や断りにくい状況を生んでしまう恐れがあります。同時依頼は失礼と受け取られることもあり、人気のある講師ほど時間調整が難しいため、混乱がおこりやすいです。一人ずつ正式に依頼し、連絡を待つ間に他の候補を探すなど、順番に検討していくのが望ましいでしょう。
講師依頼文に盛り込むべき必須項目

講師依頼文には漏れがあってはいけない重要な項目が存在します。次に挙げる要素をしっかり含めることで、講師に正しく情報を伝えることができます。
講師依頼文はビジネス上の正式な文書として扱われることが多く、最低限必要な情報を網羅することが不可欠です。宛先の敬称から目的や謝礼まで、一つでも抜け落ちていると不信感を与える原因になるかもしれません。ここでは依頼時に必ず盛り込んでおきたい項目を具体的に取り上げます。
宛名と敬称の正しい使い方
講師の氏名や肩書きに応じて、適切な敬称を用いることは基本ですが、間違いやすいポイントでもあります。“先生”を用いる場合には相手との関係性を考慮し、必要に応じて“様”などへ切り替える判断が必要です。企業所属の方の場合も、肩書きの表記に誤りがないか必ず確認し、印象を損ねないよう注意します。
講演内容・テーマと開催目的
講師に依頼する際には、イベントのテーマや目的を簡潔かつ明瞭に伝えることがポイントです。例えば「社内力の向上のため」「地域の住民向けの学習機会として」など、どのような成果を期待しているかを具体的に提示します。そうすることで、講師が準備すべき内容や方向性をイメージしやすくなり、スムーズなやりとりにつながります。
日時・場所・開催形式の具体的記載
講演やセミナーの日程はもちろん、終了予定時刻や会場の所在地、オンライン開催の場合は使用ツールなど、開催形式を事細かに示す必要があります。時間の余裕があれば、講師が下見や機材の確認をしやすいよう、会場情報やアクセス手段なども明確にしておきましょう。あらかじめ知らせておくことが、予想外のトラブル回避につながります。
謝礼や交通費・宿泊費の取り扱い
謝礼や旅費などの予算面は、最初の依頼段階で曖昧にせずはっきりと伝えるのが望ましいです。金額や支払い方法が不明瞭だと、講師側も快く引き受けにくくなりますし、後からの修正はトラブルの原因になりがちです。講師の都合と主催者の意図をすり合わせ、誠意をもって把握できるように明記しましょう。
連絡先と返信をお願いする期日の明記
主催者側の連絡先が複数ある場合は、どこに連絡してもらえばよいのか分かりやすく記載します。電話番号やメールアドレスだけでなく、担当者名も添えると混乱を防げます。さらに、返信をお願いする期日を入れておけば、講師としても自身のスケジュールを検討しやすく、互いに効率のよいやりとりが可能です。
講師依頼文の送付方法:メール・郵送・オンラインフォーム

講師依頼文の伝達手段として、メールや郵送、オンラインフォームなど様々な方法があります。ここでは、それぞれのメリットや注意点を解説します。
講師への連絡手段は多岐にわたり、相手の連絡先や好みに柔軟に合わせることが大切です。メールは手軽でスピーディーですが、相手がメールを見落としたり重要フォルダに振り分けられる場合もあります。郵送であればより正式な印象を与えられますが、到着までの時間を見込む必要があるため、返信期限などを考慮して送付方法を選びましょう。オンラインフォームはWebサービスを利用する場合などに有効ですが、講師によっては対応できないケースも想定する必要があります。
実際の講師依頼文・依頼メールの例文・テンプレート
実際の場面で活用できるよう、具体的な例文やテンプレートを紹介します。依頼する相手や目的に応じて使い分けましょう。
実際に講師へメールや手紙を送る場合は、件名や宛先の書き方、簡潔で誤解のない文章表現に気を配ります。相手がビジネスパーソンなのか、学術研究者なのか、あるいは社内の人なのかによって、用いる言い回しや詳細説明の深さが変わることも考慮しましょう。以下にいくつかの例文を挙げますので、状況に合わせて適宜アレンジしてみてください。
一般企業向けの講演やセミナーの依頼文例
ビジネススキルの向上や新しいノウハウ・知見を取り入れたい場合は、一般企業を対象とした講演が多く行われます。その際の依頼文では、従業員の属性や業界、事業目的などを簡潔にまとめて講師に伝えましょう。例として「何名規模の社員が参加するのか」「具体的にはどのような課題を解決したいのか」などを織り交ぜて文案を作成するのがコツです。
一般企業向けの講演やセミナーの依頼文例
件名:講演依頼のご相談(〇〇株式会社)
〇〇株式会社
〇〇部 〇〇様
突然のご連絡失礼いたします。
私、△△株式会社の□□と申します。
このたび、弊社主催の社内セミナーにて、〇〇に関する講演をお願いしたくご連絡いたしました。
当セミナーは社員の〇〇力向上を目的としており、約〇〇名の参加を予定しております。
つきましては、以下の内容でご検討いただけますでしょうか。
――――――――――――――――
■講演テーマ:〇〇〇〇
■開催日時:〇月〇日(〇)〇時~〇時
■開催場所:△△会議室(またはオンライン)
■謝礼:〇〇円(交通費別途)
■主催:△△株式会社
■担当者:□□(メール:xxxxx@△△.co.jp / 電話:000-0000-0000)
――――――――――――――――
お忙しいところ恐縮ですが、〇月〇日までにご返答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
――――――――
△△株式会社 □□
TEL:000-0000-0000
Mail:xxxxx@△△.co.jp
――――――――
学術分野・専門家への依頼文テンプレート
学会や研究機関、または専門的な分野の講師を招く場合は、相手の研究テーマや専門性をきちんと把握した上で文書を作成する必要があります。挨拶文では相手の功績をリスペクトし、期待する講演内容を可能な限り具体的に伝えると印象が良くなります。さらに、専門用語やデータなどを使う際は正確性に注意し、誤情報を避けるようにしましょう。
学術分野・専門家への依頼文テンプレート
件名:講演のご依頼(〇〇学会・研究会 登壇のお願い)
〇〇大学 〇〇学部
〇〇研究室 〇〇先生
突然のご連絡を失礼いたします。
私、△△学会 事務局の□□と申します。
このたび、〇月〇日に開催予定の「第〇回△△学会」において、
先生のご専門である〇〇分野に関するご講演をお願いしたくご連絡申し上げました。
本学会では、〇〇(分野・テーマ)の最新研究や実践事例を共有し、
今後の学術的発展と社会的応用について議論することを目的としております。
つきましては、先生のこれまでのご研究成果やご経験をもとに、
「〇〇〇〇(仮タイトル)」というテーマでご講演をお願いできればと存じます。
以下、概要をご確認ください。
――――――――――――――――
■講演テーマ(仮):〇〇〇〇
■開催日時:〇月〇日(〇)〇時〜〇時
■開催形式:対面(またはオンライン)
■会場:△△大学 △号館ホール(所在地:〇〇市〇〇)
■講演時間:〇分(質疑応答含む)
■謝礼:〇〇円(交通費・宿泊費別途支給)
■主催:△△学会/共催:〇〇研究所
――――――――――――――――
ご多忙の折とは存じますが、〇月〇日までにご検討の可否を
ご返信いただけますと幸いです。
何卒ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。
敬具
――――――――
△△学会 事務局
□□(氏名)
E-mail:xxxxx@△△.or.jp
TEL:000-0000-0000
――――――――
社内講師や外部派遣講師への依頼例文
企業内部の人材を社内講師として招く場合、気軽な依頼になりがちですが、正式な文書やメールを通じて丁寧に依頼することでモチベーションを高める効果があります。外部の講師派遣サービスを利用するケースでは、事務的な手続きが先方でしっかりと整っているので、主催者側としても必要事項の漏れがないよう確認しましょう。締め切りややり取りの窓口を明確にしておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
社内講師や外部派遣講師への依頼例文
件名:社内研修での講演依頼のお願い(〇〇株式会社)
〇〇株式会社
〇〇部 〇〇様
いつも大変お世話になっております。
△△株式会社 人材開発部の□□と申します。
このたび、弊社では社員向けに「〇〇」をテーマとした研修を企画しております。
つきましては、〇〇分野における豊富なご経験とご実績をお持ちの〇〇様に、
講師としてご登壇いただきたくご連絡いたしました。
以下に講演の概要を記載いたしますので、ご確認のうえご検討いただけますと幸いです。
――――――――――――――――
■講演テーマ(仮):〇〇〇〇
■開催日時:〇月〇日(〇)〇時〜〇時
■開催場所:△△株式会社 本社〇階ホール(またはオンライン)
■対象者:管理職・一般社員 計〇〇名
■講演時間:〇分(質疑応答含む)
■謝礼:〇〇円(税込・交通費別途)
■主催部署:人材開発部
■担当者:□□(E-mail:xxxxx@△△.co.jp / TEL:000-0000-0000)
――――――――――――――――
お忙しいところ恐縮ですが、〇月〇日までにご回答をいただけますと幸いです。
日程や内容の調整にも柔軟に対応させていただきますので、
ご都合に合わせてご相談ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
――――――――
△△株式会社 人材開発部
□□(氏名)
E-mail:xxxxx@△△.co.jp
TEL:000-0000-0000
――――――――
オンラインで講師を依頼する場合の注意点

オンラインイベントで講師を招く場合、 通信環境やトラブル対策など、特有の注意点があります。以下のポイントを押さえておきましょう。
近年ではオンラインツールを介した講演やセミナーが一般化しており、地理的な制約も少なく、多くの可能性が広がっています。ただし、その一方で通信障害や機材トラブルなどが発生するリスクも高まります。事前にテストやリハーサルを行うとともに、万一の際に備えて連絡体制を明示しておくことが重要です。
使用するオンラインツールの明記
ZoomやMicrosoft Teams、Webexなど、使用するオンライン会議ツールは多岐にわたります。講師に最適なツールを選定する際は、機能面や同時利用可能人数などを考慮することが大切です。ツールのインストールや設定を事前に案内し、テスト用の接続を確保することで当日のスムーズな講演を後押しできます。
通信・トラブル対策とサポート体制の確認
オンラインイベントは、回線の不具合やソフトウェアのトラブルが起きる可能性があるため、事前対策が欠かせません。予備の回線(テザリングなど)を用意したり、サポートできるスタッフを配置するなどして安全策を講じましょう。連絡先を講師へ明確に提示し、不具合が生じた場合にも速やかに連絡し合える体制を整えておくと安心です。
トラブル・断りがあったときの対応策

残念ながら依頼が断られたり、やむを得ず日程が合わないケースもあります。その際に取り得る対応策を紹介します。
講師が予定日に対応できない、あるいは条件的に難しいと判断されることも少なくありません。そうしたときに諦めるのではなく、別日程を提示して再度お願いしたり、他の講師に依頼するといった柔軟な対応も視野に入れるべきです。イベント全体の成功を考えながら、講師との関係性を円満に保つための対応策を講じましょう。
代替日程や別会場を提案する
希望の日程が合わない場合でも、同じ週や翌月など、ある程度融通が利く場合は再度交渉の余地があります。特に人気の講師であれば、日程を早めるか、場所を変えることでスケジュールの再調整が可能になるケースもあります。あきらめずに柔軟な提案を行うことが、結果としてイベントの質を高めることにつながるでしょう。
他の講師候補を検討する
依頼先が断った場合は、無理に引き止めるよりも次の講師候補を検討するほうがスムーズです。複数の候補をあらかじめリストアップしておけば、迅速に代替案を提案できます。ただし、候補を検討している段階で同時依頼は避けつつ、断られたことが確定した時点で別の講師に連絡するなど、礼儀に配慮した対応を心がけましょう。
講師依頼を外部に委託するという選択肢

講師の選定やスケジュール調整、謝礼交渉などを自社で進めるのは、時間と手間がかかるものです。
そうした負担を軽減する手段として、「講師派遣サービス」や「講師紹介会社」といった外部機関への委託があります。
ここでは、そのメリットとデメリットを整理して紹介します。
外部委託のメリット
トラブル対応や当日フォローも任せられる
契約や連絡のトラブルが発生した際にも、事務局が仲介してサポートしてくれるケースが多く、初めての主催者でも安心です。
専門スタッフが代行してくれる安心感
日程調整や謝礼交渉などの煩雑なやり取りを専門スタッフが代行するため、主催者の事務負担が大幅に軽減されます。
豊富な講師ネットワークから最適な人選ができる
多くの派遣サービスでは、実績豊富な講師データベースを保有しています。
テーマや対象者に応じて、希望に沿った講師を効率的に紹介してもらえる点が魅力です。
外部委託のデメリット
サービス利用料や仲介手数料が発生する
自社で直接講師に依頼する場合と比べて、一定の手数料がかかるのが一般的です。
予算全体に余裕を持たせることが必要です。
講師と直接やり取りしにくい場合がある
一部のサービスでは、講師との連絡がすべて事務局経由となることもあります。
細かな要望や事前打ち合わせを重視したい場合は、事前に対応範囲を確認しておきましょう。
契約条件の確認が不可欠
利用規約やキャンセルポリシーなどを見落とすと、日程変更時に思わぬ費用が発生することもあります。
契約形態は必ず事前に明確にしておくことが大切です。
外部の講師派遣サービスを活用すれば、講師探しから当日の調整までをスムーズに進められます。
一方で、コストやコミュニケーション面の制約もあるため、「自社で進めるべきか」「専門業者に任せるか」を目的と予算のバランスで判断することが重要です。
講師選びでお悩みの方へ
弊社の講師派遣サービス「Hitonova(ヒトノバ)」では、イベントテーマに合わせて最適な講師をご提案しています。
>詳しくはこちらからご相談ください

まとめ・総括:正確かつ丁寧な講師依頼文で信頼関係を築こう
講師依頼文は、講師との信頼関係の第一歩となる重要な文書です。最終的に、正確でスムーズなやり取りを実現できるかどうかは、この依頼文の完成度にかかっています。
講師にとっても、依頼文の印象はその主催者が信頼できるかどうかを判断する重要なポイントになります。講演内容や開催テーマ、日時と場所、謝礼の有無といった必要情報を過不足なく盛り込み、丁寧な表現を心がけましょう。イベントの成功は講師だけでなく、主催者側の準備次第でも大きく変わるものです。ぜひ本記事を活用し、質の高い講師依頼文で素晴らしいイベントを実現してください。
この記事のまとめ
・講師依頼文は、講師との信頼関係を築く第一歩となる重要な文書です
・イベントの目的・日時・謝礼など、必要情報を正確かつ丁寧に伝えることが成功の鍵
・依頼前の準備を怠らず、文面のトーンや敬称にも細やかな配慮を
・トラブル時は柔軟な提案で関係を円満に保つことが大切です
・講師選定や依頼対応に不安がある場合は、講師派遣サービスの利用も有効な選択肢です
Contact お問い合わせ
講師選びでお悩みの方には、目的・ご予算に合った講師をご提案します。
気になる講師のスケジュールや講演料についても、お気軽にお問い合わせください。
5営業日経過しても返信がない場合は、
恐れ入りますが電話かkouen@scg-inc.jpまでメールでお問い合わせください。

