潮匡人 うしおまさと

日本の軍事学者、ジャーナリスト/アゴラ研究所フェロー/公益財団法人 国家基本問題研究所 客員研究員/NPO法人 岡崎研究所 特別研究員/民間憲法臨調 代表委員
プロフィール
早稲田大学大学院法学研究科博士前期課程を修了した法学修士であり、航空自衛隊出身の安全保障エキスパートである。自衛隊での実務経験を背景に、国防・憲法・国際安全保障を中心とした論考を展開し、理論と現場の両面から日本の安全保障を語る数少ない専門家として知られている。
帝京大学准教授、拓殖大学客員教授などを歴任し、現在はテレビ・ラジオ・新聞・雑誌など多方面のメディアで精力的に発信している。
保守派の論客として明快かつ実証的な論調に定評があり、産経新聞「正論」欄の執筆メンバーとしても活躍。
著書に『誰も知らない憲法9条』(新潮社)をはじめ、単著・共著多数。安全保障・憲法・国家のあり方をめぐる議論において、実践的かつ現実的な視点から提言を続けている。
テーマ
出身・ゆかりの地
経歴
昭和35年3月生。早稲田大学法学部卒。同大学院法学研究科博士前期課程修了(法学修士)。
東京放送(TBSテレビ)契約社員を経て、旧防衛庁・航空自衛隊に入隊。教育隊区隊長、航空団小隊長、飛行隊付幹部、航空総隊司令部幕僚、長官官房勤務等を経て、3等空佐で退官。
クレスト社副編集長、国際研究奨学財団(東京財団)顧問、社会基盤研究所(旧長銀総研)客員研究員、聖学院大学政治経済学部専任講師、防衛庁広報誌編集長、帝京大学人間文化学科准教授、国会議員政策担当秘書、拓殖大学日本文化研究所客員教授、東海大学海洋学部講師(海洋安全保障論)等を歴任。
アゴラ研究所フェロー。公益財団法人「国家基本問題研究所」客員研究員。産経新聞「正論」欄執筆メンバー。
主な講演テーマ
緊迫化する国際安全保障と日本
世界情勢は今、戦後最も不安定な局面を迎えています。ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事の懸念、北朝鮮のミサイル発射など、国際社会の緊張は日増しに高まっています。こうした中で、日本はどのように国を守り、平和を維持していくべきなのでしょうか。
潮匡人さんは、防衛庁・航空自衛隊での豊富な実務経験と長年の研究をもとに、国際安全保障の現状と日本が直面する課題を多角的に解説します。報道では語られにくい外交・防衛の現場の実態や政策決定の背景、そして国際社会の中で日本が果たすべき役割について、わかりやすくお伝えします。
潮さんの講演は、「安全保障=軍事」という枠を超え、「国家の生存戦略」として平和と安全を考える機会を提供します。政治・経済・教育など、さまざまな分野に関わる方々にとって、今後の日本のあり方を見つめ直す貴重な内容です。
国や組織のリーダー、そして私たち一人ひとりが、これからの時代をどう生き抜くかを考えるきっかけとなる講演です。 ×
書籍・メディア出演
書籍紹介
クリックすると、詳細が表示されます。

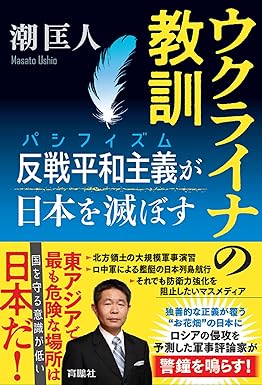
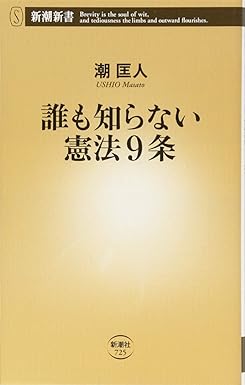
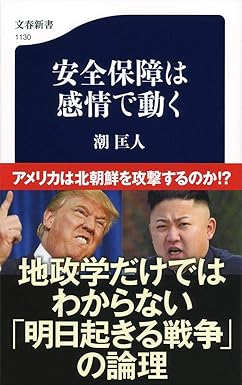

台湾有事の衝撃 そのとき、日本の「戦後」が終わる
もはや「台湾有事」はあるか、ないかの問題ではない。
それが、いつ起きるか、という問題だ。
本書は、元自衛官で、現在は舌鋒鋭い保守の論客として知られる著者が、日増しに高まる「台湾有事」の現状に迫る。
2022年の夏の中国の軍事演習から俄かに緊迫の度を増してきた台湾情勢。2023年1月、米空軍航空機動司令部のマイク・ミニハン司令官が、台湾有事を2025年に予想しているという報道が流れ、日本の安全保障論議も俄かに慌ただしくなってきた。果たして、どのようなシナリオが私たち日本人を待ち受けているのだろうか。
人気コミック『空母いぶき』の協力者である著者が警鐘を鳴らす「今、そこにある危機」。日本はウクライナの教訓を活かせるか?
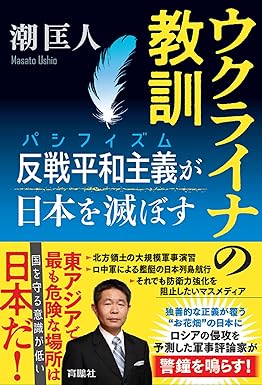
ウクライナの教訓
独善的な正義が覆う“お花畑”の日本にロシアの侵攻を予測した軍事評論家が警鐘を鳴らす!
善と悪が戦っている時に中立的姿勢をとる欺瞞。国連の機能不全が示した空想的平和主義の崩壊。日本は人間不在の防衛論議のままでいいのか? 日本の安全保障と憲法改正の問題点を指摘する。
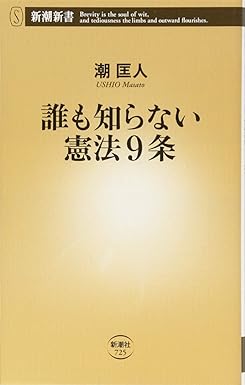
誰も知らない憲法9条
総理も、憲法学者も、わかっていない。
本当に憲法9条を読んだことがありますか?
それは本物の憲法9条ですか?
はっきり言いましょう、そんなはず、ありません
――挑発的な文章から始まる本書は、これまで論じられなかった視点を提起する。
護憲派も改憲派も、総理も共産党も目からウロコ間違いなし。
まったく新しい「9条」入門の誕生。
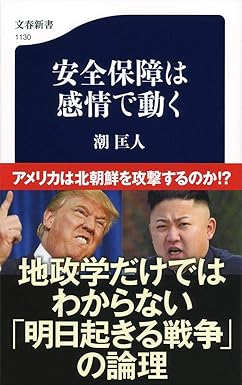
安全保障は感情で動く
近年、国際政治を読み解くツールとして地政学が脚光を浴びてきた。土地という、変更の効かない要素を軸にした地政学は、たしかに百年単位の国家戦略を考えるうえで、重要な視点である。
しかし、地政学だけで現実の国際政治を予測し、対応することは可能なのだろうか。
とくに戦争は、地政学的、言い換えれば客観的な要素だけで起きるのではない。
独裁国家であるなら独裁者の信念(もしくは誤信)、民主国家であるならば大衆の気分によって、戦闘の火蓋が切られることが多いのは、歴史が証明している。
朝鮮戦争では、南進してもアメリカは参戦してこないという金日成の誤信から始まった。外国の例を持ち出さなくても、大東亜戦争は、客観的には敗戦必至の戦争であったにもかかわらず、国民の強い声に押されて始められた。
よって、安全保障は客観性だけでなく、指導者や国民の感情といった主観的な要素が、もっとも大きなファクターになるのである。
北朝鮮が、国際情勢を無視してミサイル実験を繰り返すのも、金正恩の主観に分け入らなければ理解することはできない。そして、大方の予想(これも客観的予測)を裏切って当選したトランプ米大統領の主観も、今後の世界の安全保障を大きく左右する。
元自衛官にして安全保障の論客である筆者が長年温めてきた戦略論の決定版!
書籍
- 「安全保障は感情で動く」(文春新書)
- 「誰も知らない憲法9条」(新潮新書)
- 「ウクライナの教訓」(扶桑社・尾崎行雄記念財団「咢堂ブックオブザイヤー2022大賞(外交・安全保障部門)」)
- 「台湾有事の衝撃 そのとき、日本の『戦後』が終わる」(秀和システム)
- 実写映画化された人気コミック「空母いぶき」(小学館・累計870万部突破)シリーズに協力中
メディア
- テレビ:英BBC、独ZDF、韓国KBSほか国内外の番組出演多数。近年はテレ東「WBS」やニッポン放送「飯田浩司のOK!Cozyup!」など
- 新聞:「朝日新聞」「産経新聞」ほかコメント多数
- 雑誌:「週刊文春」「週刊新潮」「週刊ポスト」「サンデー毎日」ほかコメント多数
- 月刊誌:「文藝春秋」ほか寄稿多数
- 連載:月刊「正論」(産経新聞社)で書評欄を連載中のほか、月刊誌「諸君!」(文藝春秋)で書評欄を長期連載した。「産経新聞」朝刊で人気コラム「斜断機」と「断」を長期連載した
講演実績
政治団体
- 自由民主党、立憲民主党、日本維新の会、日本会議ほか
自衛隊関連団体
- 陸上自衛隊、航空自衛隊、小原台クラブ(防衛大学校同窓会)ほか
メディア関連
- 内外情勢調査会、「正論」懇話会(フジ産経グループ)ほか
経済労働団体
- 日本工業倶楽部(経済同友会)、ロータリークラブ、JC(日本青年会議所)、NTTグループ役員OB会、関西電力労働組合、社団法人「中央電気倶楽部」、日刊労働通信社ほか
教育関連
- 東京大学、早稲田大学、慶応大学、益田市教育委員会、成城高校ほか
この講師のおすすめポイント
潮匡人さんは、防衛・外交・安全保障の専門家として、長年にわたり日本の安全保障政策を分析・提言してきた論客である。
早稲田大学大学院で法学を修めた後、旧防衛庁・航空自衛隊に入隊し、教育・指揮・情報の各分野で実務経験を積んだ。退官後は、大学教育や政策研究の現場で安全保障や憲法問題をテーマに研究と発信を続けている。
学術的な裏づけと現場経験の両方を持つ点が潮さんの大きな特徴であり、理論と実践の両面から“日本の安全”を語る講演は、多くの自治体・企業・教育機関で高い評価を得ている。アゴラ研究所フェロー、国家基本問題研究所客員研究員としても活動中。
複雑化する国際情勢の中で、日本がいかにして国を守り、平和を維持していくか——潮さんの語りは、冷静な分析と豊富な実例によって聴講者の理解を深めてくれる。
■ 緊迫化する国際安全保障と日本の現実
米中関係、台湾情勢、ロシア・ウクライナ問題など、刻々と変化する世界の安全保障環境を解説し、日本が直面する課題と今後の選択肢を示す。国際政治の構造をわかりやすく整理し、「いま何が起きているのか」を実感できる内容。
■ 憲法と安全保障の関係を読み解く
憲法9条や自衛隊の位置づけなど、報道だけでは見えにくい法的・政策的背景を解説する。感情論に流されず、現実的な視点から「平和を守るために何が必要か」を考える機会を提供する。
■ 危機管理と組織リーダーの判断力
航空自衛隊での経験をもとに、非常時における判断・統率・情報共有の重要性を語る。企業のリスクマネジメントや防災・BCP対策にも応用できる内容で、組織運営の現場にも役立つと好評。
■ 国際社会と日本人の意識改革
安全保障は政府だけの問題ではなく、国民一人ひとりの意識にも関わるテーマである。潮さんは、教育やメディアを通じて「自国の立場を自ら考える力」を持つことの重要性を強調している。
講師の講演料について
講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。
料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。





