髙橋賢充 たかはしまさみつ

青森大学 社会学部社会学科 教授/学生相談・特別支援センター長
プロフィール
北海道大学大学院教育学研究科にて教育福祉を専攻し、社会福祉学、地域福祉学、臨床心理学、児童発達学を幅広く修める。1990年に社会福祉法人北海道社会福祉協議会に入局後、福祉相談、カウンセリング、ボランティアセンター運営、人材養成など多岐にわたる業務に従事。高齢者・障がい者・児童など幅広い対象の生活支援を行うとともに、災害時には胆振東部地震において災害ソーシャルワークを実践した。
その後、国土交通省事務官や第二管区海上保安庁健康安全対策官として、メンタルヘルス支援、カウンセリング、ハラスメント相談・教育活動を担当。また、北海道児童相談所では児童福祉司として虐待対応や発達相談に取り組むなど、現場での豊富な実務経験を積む。
教育分野では、静岡福祉大学、身延山大学、青森大学専任教員として社会福祉士・精神保健福祉士・保育士等の養成教育に携わり、北海道大学ではハラスメント専門相談員としてハラスメント予防やメンタルヘルス相談も担当。2023年より青森大学社会学部教授として、福祉専門職の人材育成に取り組んでいる。
テーマ
出身・ゆかりの地
経歴
北海道大学大学院教育学研究科で教育福祉を専攻。その他、社会福祉学、地域福祉学、臨床心理学、児童発達学。
1990年に社会福祉法人北海道社会福祉協議会に入局。北海道高齢者総合相談センター・福祉総合相談所・高齢者無料職業紹介所の相談員として勤務し、一般、高齢者、障がい者等生活支援を必要とするクライアントへの相談支援、カウンセリング等を担当。また、北海道福祉人材センター、社会福祉施設への指導、職業相談カウンセリングに従事した。北海道ボランティアセンターでは主幹を務め、ボランティアセンター運営、ボランティアコーディネーター養成・指導、ボランティア指定校に関する事務等に携わる。北海道介護実習・普及センター主幹・教務主任、地域福祉部在宅福祉課、日本ケアマネジメント学会開催企画運営ほかを担当。
2004年からは北海道社会福祉協議会地域福祉権利擁護事業空知地区事務所長を務め、北海道という広域における相談援助業務に従事。北海道胆振東部地震にて災害ソーシャルワークを実践した。
国土交通省事務官・第二管区海上保安庁健康安全対策官として、メンタルヘルス、カウンセリング、ハラスメント相談、教育活動にも従事。ほか、北海道児童相談所児童福祉司として、虐待相談対応、子どもの発達相談。
静岡福祉大学、身延山大学、青森大学専任教員として社会福祉士、精神保健福祉士、保育士等の養成教育にあたる。北海道大学では、ハラスメント専門相談員として、ハラスメント予防、メンタルヘルス相談。これらに関する講師を務めた。2023年から青森大学社会学部教授として、社会福祉士、精神保健福祉士等福祉専門職教育に従事している。
国家資格:社会福祉士、精神保健福祉士
その他資格:北海道大学大学院教育学研究科修士課程修了、日本心理学会認定心理士、公認心理士現認者講習会修了、北海道地区セクシャルハラスメント防止研修指導者養成コース修了、ハラスメント防止コンサルタント養成講座修了、スクール(学校)ソーシャルワーク教育課程専門科目群担当教員講習会修了
主な講演テーマ
職場におけるハラスメントへの対応と対策
職場で発生するハラスメント事例をもとに、組織としての適切な対応や個人が取るべき行動を解説。再発防止に向けた実践的な対策を学びます。 ×
キャンパスにおけるハラスメントをとらえる視点と予防の重要性
大学キャンパス特有の人間関係を踏まえ、ハラスメントを未然に防ぐ視点と仕組みづくりを紹介。多様な学生が安心して学べる環境整備を考えます。 ×
部下のメンタルケアのための管理職の役割
部下のメンタル不調を早期に気づき、適切にサポートするための管理職の心得を解説。信頼関係を基盤とした組織づくりに役立ちます。 ×
メンタルヘルスセミナー
企業における従業員の心の健康管理をテーマに、ストレスへの気づきやセルフケア、組織としての取り組み方を学びます。 ×
虐待を受けた生徒への対応
学校現場で直面する児童生徒の虐待問題に対し、教育現場での適切な関わり方や支援の実際を事例を交えて解説します。 ×
多様な学生に対する教育とサポート
発達障がいや外国人留学生など、多様な背景を持つ学生への教育的支援のあり方を具体的に提示し、大学教育の実践に役立てます。 ×
ある認知症高齢者の語りからこれからの生き方を考える
認知症当事者の語りを通じて、支援のあり方や地域社会との関わり方を考え、高齢社会での生き方に示唆を与えます。 ×
地域での「学び」とボランティア活動を考える
地域に根ざした学びとボランティアの役割を考え、市民一人ひとりの参加が地域福祉を豊かにする可能性を示します。 ×
支援が必要な人々を支え寄り添うことについて考える
~社会福祉専門職の知見から学ぶ~
社会福祉の現場から得られた知見をもとに、困難を抱える人々にどのように寄り添い支えるかを考えます。 ×
被災地から見えた防災の地域づくりと感染予防
被災地での経験を踏まえ、地域の防災体制と感染症対策をどう両立させるかを考える実践的な講演です。 ×
働きやすい職場づくりについて
~人間関係とコミュニケーションの視点から
学校組織における人間関係やコミュニケーションの改善を通じ、働きやすい職場づくりの方策を考えます。 ×
書籍・メディア出演
書籍紹介
クリックすると、詳細が表示されます。
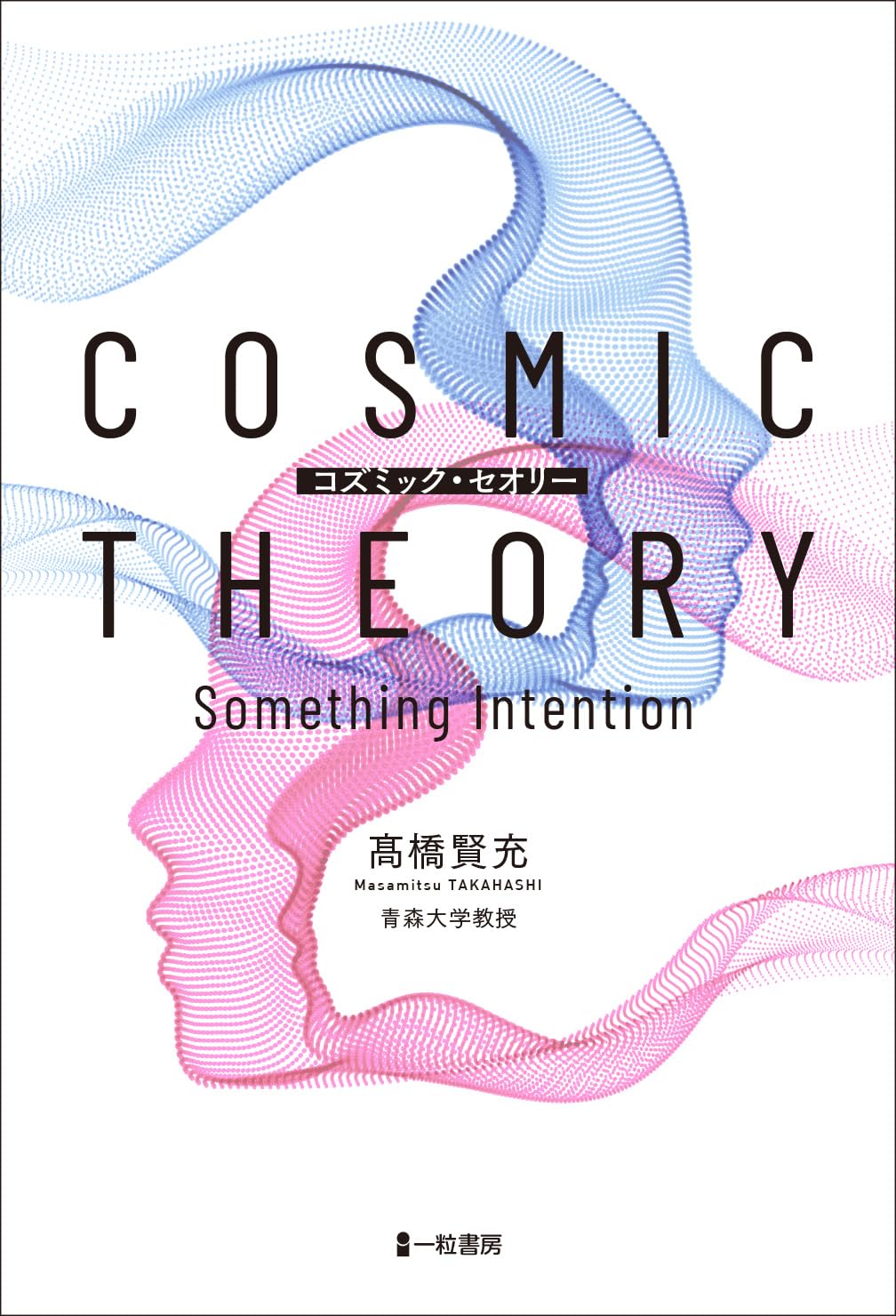
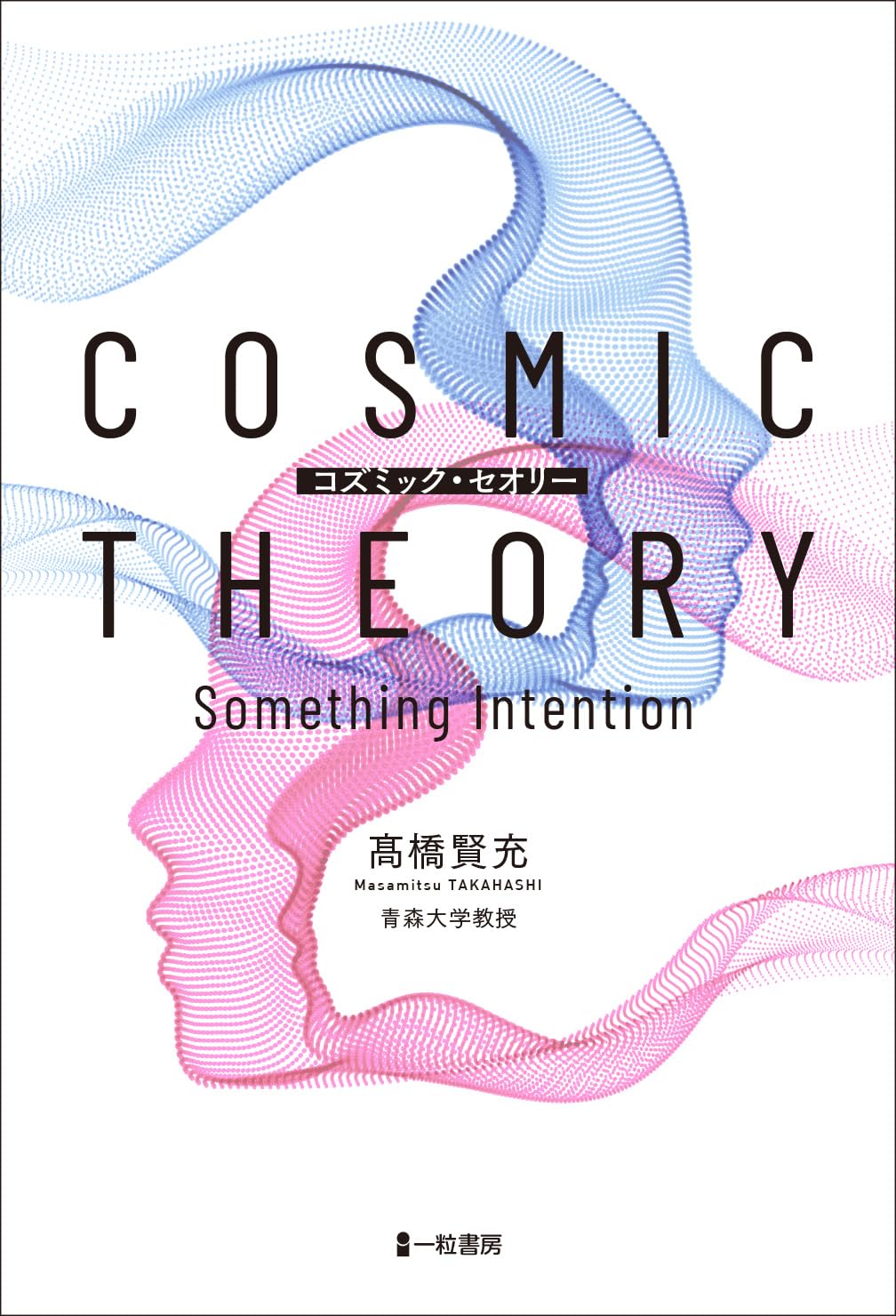
COSMIC THEORY コズミック・セオリー
著者は、35年にわたって対人援助、カウンセリングの実務の中で、人の悩みや苦しみに向き合ってきた。本書は、その実践をとおして、一人ひとりの尊厳、人権、社会正義、平和、自由に貢献するための、全人類に共通する新しいパラダイムの創造を目指して、科学や宗教、政治信条、イデオロギー、文化、民族固有の智を包摂した「人間存在の理解」のための統一理論の構築を模索したものである。
社会福祉士 相談援助演習事例集
本書は、実践の貴重な積み重ねを指針としながら、これから社会福祉士の資格取得を目指し、新たな社会福祉現場に向かい、さまざまな領域で社会福祉の援助を必要としている人々のために、その実力をつけるための教材として最適なテキストである。
書籍
- 「Cosmic Theory(単著)」
- 「子どもが育つ・つながるコミュニケーション(単著)」
- 「社会福祉士相談援助事例集(共著)」
テレビ
- NHK特集ドラマ「海底の君へ」話題提供
講演実績
団体
- 海上保安庁第二管区海上保安本部
- 北海道信用漁業協同組合連合会
- 札幌商工会議所
- 静岡市社会福祉協議会講演会
- 東青管内中学校長と東青地区高等学校長会との研究協議会
- 青森地方検察庁
- 山梨県富士北麓障害者基幹相談支援センター研修
- 日蓮宗静岡中部地区研修会
自治体
- 山梨県甲府市
大学
- 札幌国際大学
- 北海道大学国際教育センター
- 青森大学夏季教職員研修
この講師のおすすめポイント
髙橋賢充さんは、長年にわたり社会福祉の現場と教育の両分野で豊富な経験を積み重ねてきた、「福祉と人材育成のプロフェッショナル」といえる講師です。そのキャリアは30年以上に及び、北海道社会福祉協議会での相談支援業務から始まり、災害時のソーシャルワーク実践、ハラスメント防止研修、大学での専門職教育に至るまで、幅広い分野で社会に貢献してきました。
特に注目すべきは、その「多層的な経験の広がり」と「実践と理論の両立」です。北海道社会福祉協議会では、一般市民から高齢者、障がい者まで幅広い層への相談援助を担当し、福祉の現場で求められる即応力を培いました。高齢者無料職業紹介所や福祉総合相談所での活動では、生活や就労に課題を抱える人々を支え、一人ひとりに合わせた支援を行ってきました。また、ボランティアセンター主幹として、ボランティア活動の推進やコーディネーター養成にも尽力し、地域全体で支え合う仕組みづくりにも貢献しています。
その後も、地域福祉権利擁護事業所長として、広域にわたる相談援助業務に従事。特に北海道胆振東部地震では、災害ソーシャルワークを現場で実践し、被災者の生活再建支援に取り組みました。災害時の混乱した状況においても、生活課題を的確に見極め、必要な支援へとつなげる経験は、他の専門家ではなかなか得られない貴重な財産と言えます。
また、国土交通省や海上保安庁といった行政機関においても活躍し、メンタルヘルスやハラスメント相談に従事しました。ここでは、公務員や管理職といった立場の人々に対するカウンセリングや予防的な教育活動を展開。職場における人間関係の改善や風通しの良い職場環境づくりをテーマに研修を行うなど、福祉の視点を組織マネジメントにも応用してきました。これは、福祉現場だけでなく、あらゆる職場に共通する「人の心を守り、働きやすい環境をつくる」という課題に対して、極めて実践的な知見を提供できる強みとなっています。
教育分野においても、静岡福祉大学、身延山大学、青森大学などで専任教員を務め、社会福祉士や精神保健福祉士、保育士など次世代の福祉専門職を育成してきました。理論教育にとどまらず、自らの豊富な現場経験を踏まえた具体的な事例や実践的スキルの指導を行うことで、学生たちに「現場で役立つ学び」を提供している点が大きな魅力です。さらに北海道大学ではハラスメント専門相談員として活動し、教育現場における予防策の整備や学生のメンタルケアにも深く関わりました。
研修や講演テーマも非常に幅広く、ハラスメント防止、メンタルヘルス、虐待対応、発達障がいへの理解と配慮、災害ソーシャルワーク、地域づくりなど、多岐にわたります。例えば「職場におけるハラスメントへの対応と対策」「部下のメンタルケアのための管理職の役割」などは、企業や行政機関が直面する喫緊の課題に対して実効性のあるアプローチを示すものであり、高い評価を得ています。また、「災害時の生活課題とソーシャルワーク」や「虐待を受けた生徒への対応」といったテーマは、専門職に求められる実践力を養ううえで非常に有益です。
資格面でも、社会福祉士、精神保健福祉士、日本心理学会認定心理士、公認心理士現認者講習修了など、相談援助や心理支援に関わる国家資格・認定資格を多数有しています。さらに、ハラスメント防止やスクールソーシャルワークに関する研修課程を修了しており、福祉、心理、教育、組織マネジメントの領域を横断的にカバーできる点が大きな強みです。
総じて、髙橋賢充さんの魅力は「福祉の現場」「行政機関」「教育現場」という三つのフィールドを横断し、人を支える仕組みを理論と実践の両面から構築してきたことにあります。虐待や発達障がいといったデリケートな相談支援から、職場のメンタルヘルスやハラスメント防止、さらには災害時の緊急対応まで、多様なテーマに対応可能です。そのため、企業研修や自治体事業、教育機関の研修など、どの場においても的確で実践的なアドバイスを受けられるでしょう。
講師の講演料について
講演料は、講演内容・開催場所によって異なるため、非公開としています。
料金の目安については、お気軽にお問い合わせください。





