Special 講師へのお礼状・お礼メールの正しい書き方と例文|講演会後に失礼のない伝え方
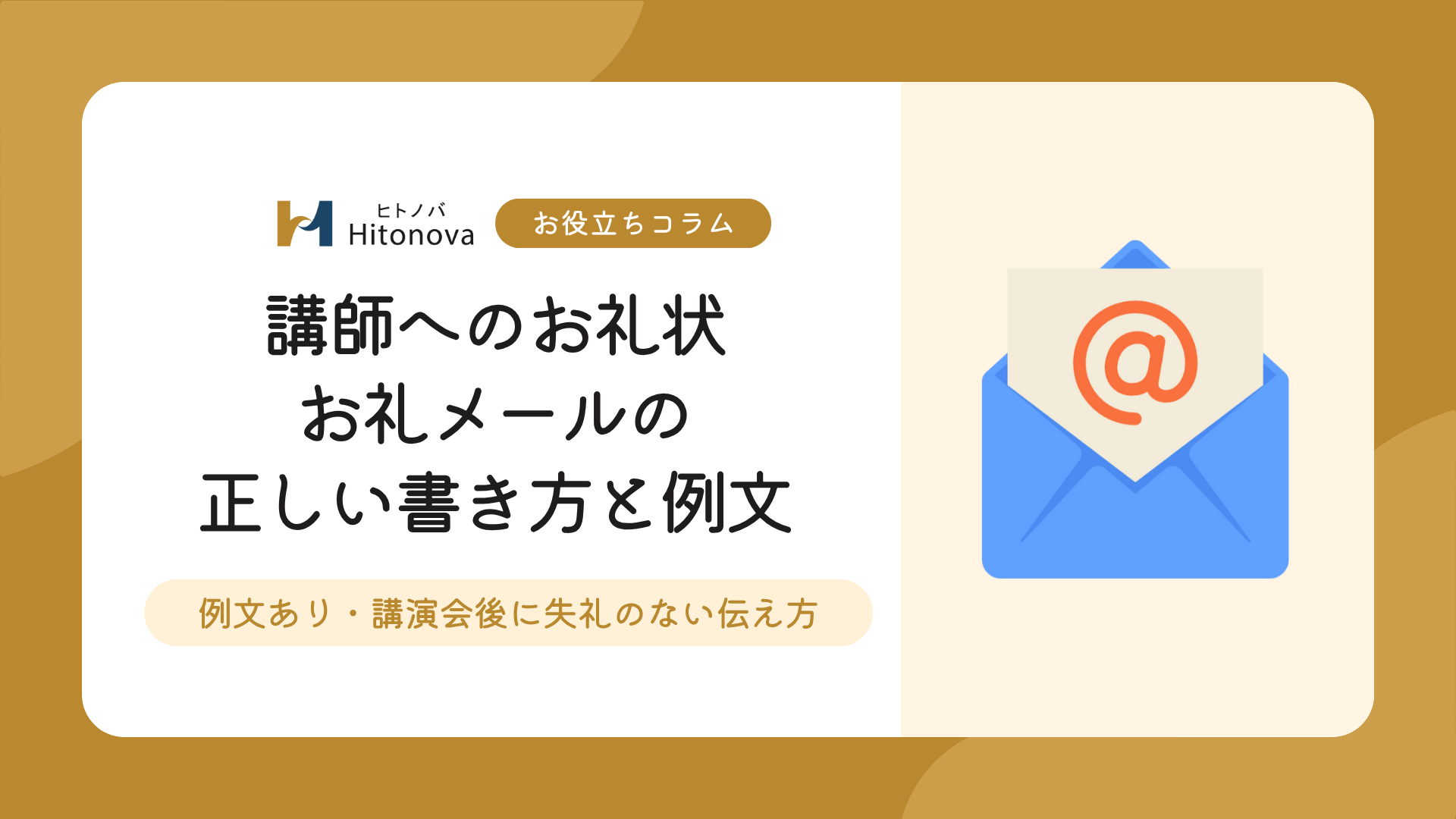
講師へのお礼状は、感謝の気持ちを伝えるとともに、今後の良好な関係を築くためにも重要なものです。ここでは、お礼状が果たす役割から具体的な書き方・例文、送るタイミングなど、押さえておきたいポイントを網羅的にご紹介します。
一度教えていただいた知識や学びを、さらに定着させていくためにも、講師へのお礼状は大事な役割を果たします。実際に感謝の言葉を文章で伝えることで、相手に信頼と敬意を示すと同時に、今後も継続的なご指導をお願いしやすくなります。
また、お礼状を送ることで講師側にも、自分の講義や講演がどのように受け止められ、役立っているかを伝えるきっかけを作れます。適切なタイミングと内容で感謝を伝えれば、次回の講演やセミナー開催時にもスムーズなやり取りが実現しやすくなるでしょう。
講師への感謝が、次のご縁をつくる
講師へのお礼状だけでなく、講演依頼から当日の運営サポートまでトータルで支援しています。
初めての講演主催でも安心。
👉 講師派遣サービス「Hitonova」で詳細を見る
お礼状が必要な理由と基本的な役割

講師への感謝や学びを共有することで、信頼関係を育み、今後の協力体制を確立するきっかけになります。
お礼状を送る大きな理由の一つは、講師が提供してくれた専門知識や体験談、指導への感謝を具体的に表すためです。講師にとっても、自身の講義や講演がどんな学びを与えたのかを知れる機会になるため、両者がお互いにポジティブなフィードバックを得られます。
また、お礼状はそれ自体がコミュニケーションツールとして役立ちます。直接会う機会が限られる場合でも、文面を通じて丁寧な印象を残すことができれば、次回のイベントやセミナーでも協力関係を築きやすくなるでしょう。
さらに、お礼状を書く過程で自分が得た学びを振り返ることができるのも大きなポイントです。ただ単に感謝を伝えるだけでなく、学びを整理し会得した内容を深く理解するきっかけにもなるため、学習効果を高める意味でも有効です。
お礼状の形式はメールか手紙か?

お礼状を送る際、メールと手紙のどちらを選ぶべきかは目的や相手との関係性によって異なります。それぞれの特徴を把握しましょう。
メールであれば簡便かつスピーディに感謝を伝えられ、手紙であればより丁寧で特別感のある文面を送りやすい特徴があります。どちらの形式でも大切なのは、相手の講師が読みやすく、そして内容に真心を感じられる文章を心がけることです。
もし講師が若手やSNS・メールでの連絡に慣れている場合は、まずはメール形式を選ぶとストレスなく伝わりやすいでしょう。一方、伝統的な礼儀や手書きの文章を好む相手には、手紙にすることでより感謝の気持ちが伝わりやすくなるケースもあります。
最終的には、どのような形が相手に適切かを見定めたうえで、相手が喜びそうな形式で送付するのがポイントです。状況を考慮し、失礼のない形で選択するようにしましょう。
メールのメリット・デメリット

メールは即時性が高く、相手にすぐに感謝の意を伝えられるのが最大のメリットです。講演会やセミナーの直後など、記憶が鮮明なうちに連絡できるため、感謝のニュアンスが伝わりやすいでしょう。
一方で、メールは手軽に送れる分、文章が簡潔になり過ぎたり画一的な印象を与えてしまう恐れもあります。講師からすると“定型文を送られただけ”という感覚を持つ可能性もありますので、きちんと個別の学びや感想を盛り込む工夫が必要です。
また、講師の受信環境によっては埋もれるリスクもあるため、件名や冒頭文はわかりやすく要点をまとめるようにしましょう。短すぎず長すぎない分量で感謝と学びをきちんと伝えることが理想です。
手紙のメリット・デメリット

手紙は、手間をかけて用意する分、温かみや真心が伝わりやすく、相手の記憶に残りやすいのが大きなメリットです。講師を敬う気持ちや深い感謝を改まった形で表現できるため、場合によっては非常に好印象を与えることができます。
しかし、投函や郵送の手間がかかるため、到着までに時間がかかる点には注意が必要です。講演やセミナー後に内容をまとめて送る場合はタイミングが遅れないようにし、遅れてしまう場合は一言添えてお詫びを述べるなどの配慮を加えると良いでしょう。
また、手書きの場合は書き損じや筆記具の選択にも気を配る必要があります。きれいな文字で書ききれない場合はパソコンで文章を作成し、印刷して署名だけ手書きにするなど、無理のない形で失礼のない文面を目指すことが大切です。
お礼状を送るタイミングと書き方の基本マナー

お礼状はタイミングが大切です。また、宛先や署名など、基本的なマナーを守ることで相手に失礼にならないようにしましょう。
講師へのお礼状は、できる限り早い時期に送ることが要となります。特にメールの場合は当日から翌日、手紙の場合でも1週間以内を目安に送ると良いとされています。感謝を新鮮なうちに伝えることで、講師の印象にも残りやすく、お互いの関係もスムーズに続いていくでしょう。
また、文章の作成にあたっては、誤字脱字がないか必ず確認し、失礼のない敬語表現を意識する必要があります。開催日や講師の正式な肩書きを間違えないようにするのもマナーとして重要です。
最適な送付時期
メールなら当日や翌日に送ることで、講師も講演やセミナーの手ごたえを鮮明に思い出しやすく感謝を伝えられます。手紙を選ぶ場合は、送付のタイミングが遅くなりがちなので、セミナー後から1週間以内を目安に行動するようスケジュールを組んでおくと安心です。
何らかの都合で送付が遅れてしまった場合は、その旨を一言文面に含め、遅れたことに対するお詫びを伝えるのがおすすめです。気遣いをしっかりと示すことで、相手への敬意を失わずに関係を維持できます。
特に人気の講師や忙しい方の場合、時間が経てば経つほど記憶もあいまいになりがちです。できるだけ早い段階で書面を送ることで感謝の思いをはっきりと伝えられ、今後のやり取りに好影響を与えます。
宛先・署名・連絡先の書き方
宛先には、必ず講師の正式な肩書きとフルネームを記入し、敬称を正しく使うようにします。肩書きを省略してしまうと失礼になる可能性があるため、招待状やセミナー案内などに記載されているものを確認しましょう。
また、差出人欄には自分の氏名とともに、所属や連絡先をわかりやすく明記するのが理想的です。メールでも手紙でも、署名の最後に連絡が取りやすい電話番号やメールアドレスを記載すると、次のやり取りにスムーズにつなげられます。
書式は文面の体裁によって若干異なりますが、読みやすさを心がけるのが最優先です。講師がスムーズにあなたのことを思い出せるように、セミナー名や実施日時なども付け足しておくと親切でしょう。
お礼状の文章構成と押さえておくべきポイント

お礼状の構成は独特で、前文・主文・末文それぞれに配慮した文章を書きましょう。言葉選びも重要です。
お礼状では、前文で時候の挨拶や講師へのねぎらいの言葉を伝え、主文で感謝と具体的な学びを述べ、末文で今後の展望や講師の健康を気遣う言葉を加えるのが基本的な流れとなります。書状・メールともに、まずは最大限の敬意を伝えるとスムーズに読み進めてもらいやすくなります。
専門的なセミナーや講演であった場合には、学びになったポイントを具体的に盛り込むと、講師にも大きな励みになるでしょう。なお、あまり長文になりすぎると読む負担を与えてしまうため、適度に段落を分けて軽快さも意識することが大切です。
大前提として感謝の意味が伝わることが最優先ですが、単に形式的なフレーズの羅列にならないよう、講演全体で特に勉強になった部分や具体的なエピソードを入れると印象的になります。そうすることで講師に再度講演をお願いする際にも前向きな返答が得やすくなります。
前文・主文・末文の構成
前文では季節や近況に触れる文を軽く入れながら、講師が活躍されている様子や健康を気遣う一文を添えるのが適切です。主文に入るときには、講義の具体的な内容に対する感想や学びを述べ、どのように役立てたいかを記すことで講師の貢献度を強調します。
末文では重ねて感謝の気持ちを強調すると同時に、今後の関係継続や再度のご指導をお願いしたい旨を伝えましょう。文末には、講師の益々の発展と健康を願うような結びの挨拶を入れるのが一般的です。
特に手紙の場合、書式に気を配りながら各段落を意識的に区切ると読みやすくなります。時候の挨拶から入り、感謝と報告、最後の御礼という流れを守ることが、正式な書状としての格式を保つポイントです。
好印象を与える言葉選び
感謝の言葉や敬語表現は、お礼状の核となる要素です。例えば「貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます」「大変勉強になりました」「今後ともご指導をいただけますと幸いです」など、敬意を忘れず具体的に伝えると好印象につながります。
また、実際に反響が大きかった部分については「参加者からはもっと詳しく聞きたいという声が多く上がりました」と書くなど、講師が成果を実感できるようなフレーズを取り入れると良いでしょう。肯定的な表現を多用することで、一層感謝の意が伝わりやすくなります。
過度に堅苦しくなりすぎる必要はありませんが、謙虚な姿勢と前向きな気持ちがうかがえる言葉選びを心がけましょう。感謝だけでなく、今後の展望や期待も添えることで、講師にも次の機会へのモチベーションを感じてもらえるはずです。
次の講演も成功へつなげるために
お礼状をきっかけに、講師との関係を深めませんか?
Hitonovaでは、講演依頼・再登壇のご相談もスムーズに行えます。
ご希望のテーマや講師に合わせて最適なプランをご提案します。
👉 講師紹介を見る
ケース別お礼状例文集

セミナーと講演会での状況に応じたお礼状の例文を確認してみましょう。
実際に言葉を交わす機会が少なかった場合でも、セミナーや講演会終了後にお礼状を送ることで、自分がどれだけ学びを得たかをきちんと伝えることができます。以下の例文では、想定する状況に応じた文章の組み立てを参考にするとスムーズでしょう。
例えばセミナーの場合は受講生の具体的な反応を伝えたり、講演会の場合は会場の熱気や参加者の声を盛り込むと好印象を与えやすくなります。また、必ずしも長文にする必要はありませんが、要点を押さえて丁寧な文章でまとめることが大切です。
ここから紹介する例文はあくまで一例なので、実際の講師やシーンにあわせてアレンジしてください。特に学びになった内容や新たに芽生えた疑問などを具体的に盛り込み、講師が書いてよかったと思えるような内容に仕上げると良いでしょう。
セミナー講師への例文
セミナーや研修を実施した後、講師へのお礼状を送ることで、感謝の気持ちを伝えると同時に、次回以降の協力関係をより強固にできます。
特に、講師へのお礼メールやお礼状の書き方を押さえておくことで、社会人としての信頼感を高め、企業イメージの向上にもつながります。
以下は、実際に使える丁寧な文面のテンプレート例です。
時候の挨拶や感謝の言葉、学びの具体的な内容を自然に盛り込むことで、誠意の伝わるお礼状になります。
セミナー講師へのお礼状テンプレート
拝啓 〇〇の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
先日は、当社セミナーにてご講演を賜り、誠にありがとうございました。
参加者からは「_____________________」などの声が多く寄せられ、
大変有意義な時間となりました。
今回のセミナーで得た学びを今後の業務や活動に活かし、
一層の成長につなげてまいりたいと存じます。
今後ともご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
末筆ながら、先生のますますのご活躍とご健康をお祈り申し上げます。
まずは略儀ながら書中にて御礼申し上げます。
敬具
講演会講師への例文
講演会終了後に講師へお礼状を送ることは、感謝の気持ちを伝えるだけでなく、
今後のご縁をつなぐ大切なビジネスマナーです。
以下では、季節の挨拶から締めくくりまで、丁寧かつ印象に残るお礼状のテンプレートを紹介します。
そのまま使える構成なので、メール・手紙どちらにも応用可能です。
講演会講師へのお礼状テンプレート
拝啓 〇〇の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
先日は、○○講演会においてご講演を賜り、誠にありがとうございました。
参加者からは「_____________________」などの感想が多く寄せられ、
学びの多い貴重な時間となりました。
先生のご講演を通じて、私たちはテーマの重要性を改めて実感し、
今後の活動においても大きな指針を得ることができました。
これからも学びを深め、日々の業務や組織運営に活かしてまいりたいと存じます。
ご多忙の中、貴重なお時間を割いていただき、心より感謝申し上げます。
先生のますますのご発展とご健勝をお祈り申し上げ、
まずは書中にて御礼申し上げます。
敬具
メールでのお礼状テンプレート
メールでのお礼状は簡潔かつわかりやすい表現が大切です。ポイントを押さえたテンプレートを使ってスムーズに送りましょう。
メールでお礼状を送る場合は、相手の時間を奪わずに要点を伝えることが重要です。できるだけ簡潔にまとめながらも、感謝や具体的な学びの内容をしっかり盛り込みましょう。あらかじめテンプレートを用意しておくと、忙しいときでも失礼のない文面を作成できます。
ただし、テンプレートを使うからといって定型文のような印象を与えないよう、一言でも個別のエピソードや講師の方への感想を加える工夫が求められます。感謝の気持ちがしっかり伝わるよう、件名から結びにかけて誠意を表す表現を心がけてください。
また、署名や連絡先をきちんと明記しておくと、講師からの返信をスムーズに受け取れます。必要に応じて次回の打ち合わせや追加質問などに対応できるよう、連絡を取り合いやすい環境を整えることも大切です。
講師へのお礼メールテンプレート
件名:先日の講演会御礼(〇〇株式会社/〇〇)
〇〇先生
お世話になっております。〇〇株式会社の〇〇と申します。
先日は「〇〇講演会」にて貴重なお話をいただき、誠にありがとうございました。
特に_________________________________点が印象的で、
参加者からも「__________________________」と好評の声が多数寄せられました。
今回のご講演を通じて多くの学びを得ることができ、
今後の業務にも早速活かしていきたいと考えております。
またご指導を賜る機会をいただけますと幸いです。
改めまして、このたびのご厚意に心より感謝申し上げます。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
──────────────────────
〇〇株式会社 〇〇部
氏名:〇〇 〇〇(フルネーム)
電話:000-0000-0000
メール:hitonova@xxxx.co.jp
──────────────────────
件名・本文で気をつけたいポイント
メールの件名は「〇〇セミナー御礼」「先日の講演の御礼」など、ひと目で内容が分かるシンプルなものにするのが鉄則です。講師が多くのメールを受信する中で目立ち、かつ失礼のない表現を選ぶようにしましょう。
本文では冒頭に感謝の気持ちを述べ、セミナーや講演会で得られた学びを簡潔にまとめます。講師にとってどう役立てたいのかを添えると、相手にとってもやりがいを感じやすい内容となるでしょう。
結びの言葉で改めてお礼を伝えるとともに、今後の連絡についても一文添えておくのがおすすめです。署名には自分の氏名と所属、連絡先をしっかり入れておくと、講師とのやりとりが格段にスムーズになります。
感謝の気持ちを明確にするフレーズ例
「先日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」「大変勉強になるご講演で、社内でも大きな話題となっております」など、具体的な内容を含むフレーズを用いると一層感謝の気持ちが伝わります。
「本当に参考になり、早速社内で活かしていきたいと考えております」「今後の業務に活用できる内容が多く、改めて感謝申し上げます」といった前向きな表現も好印象を与えやすいです。可能であれば、どのように活かす予定なのかを併記すると、講師にも役立った実感を持ってもらえるでしょう。
講師に対してさらなる指導や協力をお願いしたい場合は、「今後ともご指導をいただけますと幸いです」「引き続きご相談させていただく機会をいただければ幸甚です」などの謙虚な表現を加えることでスムーズな関係性を築きやすくなります。
まとめ・総括
ここまでご紹介したポイントを踏まえ、早めのタイミングで心のこもったお礼状を準備しましょう。相手と良好な関係を築くための重要なステップとなります。
お礼状を送るタイミングや形式、文章構成は、講師への敬意を示すうえで外せない要素です。メールか手紙かを選ぶ際も、講師や状況に合った手段を吟味し、失礼のないよう配慮することが大切です。
お礼状の本文では、具体的に学んだ内容や感謝の気持ちを簡潔かつ誠実に伝えることで、相手に再度の登壇や指導をお願いするときもスムーズなやりとりが可能になります。講師にとっても、どんな価値や効果をもたらしたのかが分かるため、双方にメリットがあります。
何より、感謝の気持ちを伝えることは人間関係を円滑にする第一歩です。最適な時期を逃さずにお礼状を用意し、講師に敬意と真心をしっかり届けることで、今後の学びの機会をさらに広げていきましょう。
講師との良い関係を、次の学びへ。
講演会を通じて得たご縁を次の機会へ発展させるなら、講師派遣サービス「Hitonova」が便利です。
講師選定から打ち合わせ、当日のサポートまでワンストップで対応。
あなたの「感謝」を次の「成功」へつなげます。
👉 Hitonovaで講演依頼を相談する
Contact お問い合わせ
講師選びでお悩みの方には、目的・ご予算に合った講師をご提案します。
気になる講師のスケジュールや講演料についても、お気軽にお問い合わせください。
5営業日経過しても返信がない場合は、
恐れ入りますが電話かkouen@scg-inc.jpまでメールでお問い合わせください。

