Special 講師紹介の完全ガイド|基本構成・例文・注意点まで徹底解説
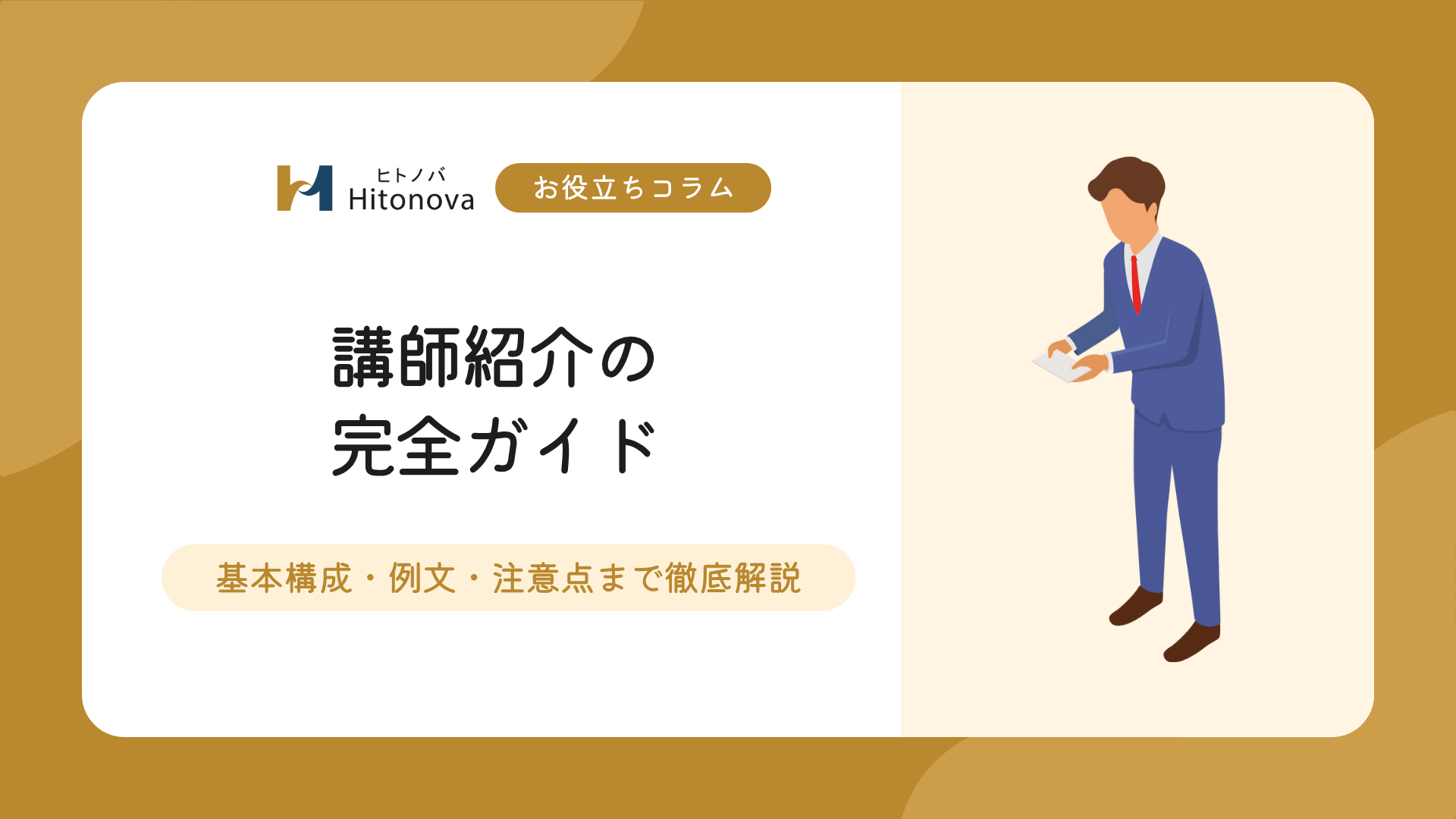
本記事では、講師紹介がどのような目的と役割を持ち、どんな基本情報を盛り込むべきかを解説します。さらに、各パターン別の具体的な紹介文例や作成する際の注意点、オンラインイベントへの応用などをまとめました。講師紹介を適切に行うことで、イベントの魅力や講師の専門性を最大限に活かすことができます。ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
・講師紹介の目的とその役割
・講師紹介文に盛り込むべき基本項目
・構成と進行の流れのポイント
・職業別に見る講師紹介文の実例
・作成時の注意点とトラブル防止策
・成功するための準備ポイント
・オンライン講師紹介の方法と注意点
・講師情報の管理方法と派遣サービス活用のコツ
講師紹介が果たす役割と重要性

講師紹介は、イベントや講演会の質を大きく左右する重要な要素です。その役割と意義を解説します。
講師紹介は、主催者だけでなく参加者にとっても極めて重要な意味を持ちます。なぜなら、講師がどのような経歴や実績を持つかを理解することで、聴衆の興味や期待値を高めることができるからです。同時に、講師としても自分の専門性を認知してもらい、講演の理解を深めてもらうための入り口となります。
実際に会場やオンラインで講演を行う場合、最初の数分で参加者の集中度が大きく変わると言われています。講師紹介がきちんと行われることで、その講師の立ち位置や専門性を明確に示し、聴衆が安心して話に耳を傾けられる環境をつくり出すことが可能です。
さらに、講師紹介はイベント全体のブランディングにも影響を及ぼします。講師が有名な経営者なのか、大学教授なのか、あるいは現場で活躍する専門家なのかを的確に伝えることで、イベントの質や目的を明確に示すことができます。こうした効果が期待できるため、講師紹介が果たす役割は決して軽視できません。
講師紹介に含めるべき基本項目

講師紹介文には、講師の経歴や講演内容など必ず伝えたいポイントがあります。その基本構成を確認しましょう。
講師紹介文を作成する際には、講師のフルネームや肩書き、略歴、現在の活動内容、講演テーマといった基本的な情報をわかりやすくまとめることが重要です。初めて名前を聞く人であっても、講師のバックグラウンドがすぐにイメージできるように書き込むことで、イベントや講演会の内容をスムーズに受け止めてもらう効果があります。
また、ネット上で得られる非公式の情報や憶測は避け、公式サイトや講師本人から直接得た正確な情報のみを使用することが基本です。これは信頼性を確保するために必須のプロセスであり、講師の実績を正しく伝えるためにも欠かせません。
講師の名前・肩書き
講師の名前や正式な肩書きは、紹介文の最初に明確に示しましょう。肩書きは企業の代表なのか、大学教授なのかなど、講師の専門性や立ち位置を端的に表現するポイントでもあります。間違った名称や敬称の使い方をすると、講師本人や参加者からの信頼を損ねかねません。
特に、医療系や学問系などの場合は、学位や所属機関を正確に伝えることで、専門性を強くアピールすることができます。一方、経営者やタレントなどの場合は、企業名や出演番組などの肩書きがわかりやすいキーとなる場合もあるため、状況に応じて適切な肩書きの提示を行いましょう。
略歴と主な実績
略歴では、過去の学歴や職歴、受賞歴など講師の歩んできた道のりを手短にまとめます。このプロフィール部分をしっかりと記載することで、講演者への期待感を高めることができるのが大きな利点です。
企業経営者の例であれば、どんなビジネスを成功に導いたのか、専門家であればどの分野の研究や活動で評価を得ているのかを具体的に示します。実績に関して誇大表現をせず、正確さを重視することが大切です。
現在の活動内容
講師の今現在の活動に関して記述することは、聴衆にとっての“最新”情報を得るうえで重要です。実際にどのようなプロジェクトや研究を進めているのかを知ることで、より深い興味を惹くことができます。
例えば、著作の出版を続けているのか、新技術開発に取り組んでいるのか、テレビ出演などの広報活動を積極的に行っているのかなど、講演時点での講師の姿をイメージできるようにまとめましょう。
今回の講演テーマ
最後に、当日の講演テーマや目的を簡潔に伝えます。ここで聴衆の関心を引くフックを入れることで、「なぜ今回この講師が選ばれたのか」を明確にアピールすることが可能です。
テーマがビジネス系であれば、経営ノウハウや成功事例の話が中心になることを伝えたり、スポーツ選手であればメンタルトレーニングやチームワーク論の視点で話すなど、興味を引く表現を取り入れましょう。
講師紹介文の基本構成と流れ

講師紹介を円滑に進めるために、プログラム内での流れを整理しておくことが大切です。
講演会やセミナーでは、全体のタイムスケジュールの中に講師紹介を組み込みます。プログラム冒頭で行うのが一般的ですが、イベント運営の都合や講師のリクエストに応じて適宜変更することもあります。
流れをスムーズにするためには、司会担当と講師本人が「どの時点で紹介を行い、どうやってステージへ招くのか」「講師本人が補足説明を加えるタイミングはどこなのか」を事前に共有しておくことがポイントです。
開会の挨拶と諸注意
イベントやセミナーの冒頭では、司会者や主催者から開会の挨拶と諸注意を伝えることが通例です。具体的には、イベントの主旨や進行スケジュール、会場での撮影や録音ルール、オンラインであればミュートやカメラのオン・オフの設定などが含まれます。
これらの案内を短すぎず、かつ要点がわかりやすいかたちで伝えることで、聴衆が混乱なく講演を楽しめる環境を整えられます。
講師の呼び込みと演題の紹介
開会の挨拶が終わったら、次に講師を迎えるタイミングとして講師紹介を行います。講師の名前や略歴、さらに今回の演題をシンプルに発表し、登壇を促すのが一般的です。このとき、呼び込む言葉や口調によって、会場の雰囲気や講師の登場シーンに大きな影響を与えるため、丁寧かつ元気な口調を意識しましょう。
演題の紹介では、特にタイトルが参加者の興味を引く内容かどうか、どのように聞き手にメリットがあるかを簡潔に伝えることが効果的です。
講演終了後の質疑応答・締めの挨拶
講演が終わった後は、質疑応答の時間を設けることで聴衆とのコミュニケーションが深まります。質問を受け付ける形を予め着席型にするのか、チャットで受け付けるのかなど、進行方法やルールを明確にしておきましょう。
質疑応答の後は、司会者からお礼の挨拶や今後のイベント情報などを伝えて締めくくります。最後に、拍手やリスペクトの気持ちが自然に生まれる雰囲気を作ることが重要です。
パターン別・講師紹介文の例文

講師の職業や肩書きに応じて、紹介文には異なる工夫が必要です。具体例を挙げて解説します。
講師の専門分野が経営、学術、スポーツ、芸能などさまざまに渡る場合、それぞれで着目すべき経歴やエピソードが異なるのは当然のことです。誰しもが知っているメディア露出や目覚ましい実績があれば、それを強調するのが有効です。
一方で、知名度がまだ高くない講師の場合には、「どのような独自の視点や専門性を持ち合わせているのか」を紹介文でうまく伝えることで、関心を高めることができます。
経営者の講師紹介例
経営者を紹介する場合は、立ち上げた企業や事業規模、過去に築き上げた実績をしっかりと示すとよいでしょう。例えば、「スタートアップ企業を立ち上げ、わずか3年で年商数億円の事業を展開」などの要素があると聴衆の興味を強く引きます。
また、経営者ならではの失敗談やビジネスの変遷についても触れると、リアリティが増し、聴衆との共感につながりやすくなります。
経営者の講師紹介例
本日の講師、〇〇株式会社 代表取締役の 〔講師名〕 さんをご紹介いたします。
〔講師名〕さんは、〇〇年に〇〇業界で起業され、現在は全国に〇〇拠点を展開するなど、
着実に成長を続けてこられました。
創業からわずか〇年で年商〇〇億円を達成するなど、その経営手腕は多方面から注目されています。
一方で、創業期の苦労や失敗から得た学びも率直に語られており、
経営者としての実体験に基づくお話には、多くの共感と気づきが込められています。
本日は「〔講演タイトル〕」というテーマで、
これまでの歩みの中で培われた経営の哲学や、これからの時代を生き抜くためのヒントをお話しいただきます。
それではご登壇いただきましょう。
〇〇株式会社 代表取締役 〔講師名〕 さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
ジャーナリスト・評論家の講師紹介例
ジャーナリストや評論家の場合、社会問題や政治・経済などの分野を専門的に追い続けている実績を盛り込むと効果的です。過去の取材経験や出演番組などを短くまとめることで、その発言の裏付けを示すことができます。
情報を客観的に整理する立場ならではの視点は、多くの参加者に新しい気づきを与える可能性が高いので、その価値を強調する紹介が大切です。
ジャーナリスト・評論家の講師紹介例
本日の講師、〔講師名〕 さんをご紹介いたします。
〔講師名〕さんは、長年にわたり〇〇(例:政治・経済・国際情勢など)の分野を専門に取材・分析されており、
これまでに〇〇新聞・〇〇テレビ・〇〇誌など多くのメディアで活躍してこられました。
現在は、〇〇大学で非常勤講師として教鞭を執るほか、執筆活動や講演を通じて、
社会問題をわかりやすく解説するジャーナリストとして幅広い支持を集めていらっしゃいます。
膨大な取材経験と鋭い分析力に基づいたお話は、
日々のニュースを新しい視点から捉え直すきっかけを与えてくださいます。
本日は「〔講演テーマ〕」をテーマに、
現場で見てきたリアルな事例と今後の社会のあり方についてお話しいただきます。
それではご登壇いただきましょう。
ジャーナリストの 〔講師名〕 さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
芸能人の講師紹介例
芸能人が講演を行う場合は、テレビ番組や舞台での活動実績をわかりやすく伝えることがポイントです。新規ファンやライト層でも知っている代表的な出演作や受賞歴にふれると、親近感を与えることができます。
また、芸能の仕事を通じて得られた人生観や社会的メッセージなどを盛り込むと、エンターテインメント以外の部分でも参加者に有益な内容があると感じてもらえるでしょう。
芸能人の講師紹介例
本日の講師、〔講師名〕 さんをご紹介いたします。
〔講師名〕さんは、〇〇年にデビューされて以来、
俳優・タレントとして数多くのテレビ番組や映画、舞台に出演されてきました。
代表作には「〔出演作品名〕」や「〔出演番組名〕」などがあり、
幅広い世代から親しまれています。
芸能活動を通して多くの人と出会い、様々な経験を積まれてきた〔講師名〕さんは、
現在では講演活動にも力を入れられ、人生の転機や仕事への向き合い方、
そして心のあり方について多くのメッセージを発信されています。
本日は「〔講演テーマ〕」というテーマで、
芸能活動を通じて得られた人生観や、挑戦・再出発のストーリーをお話しいただきます。
それではご登壇いただきましょう。
〔講師名〕 さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
スポーツ選手の講師紹介例
スポーツ選手の場合は、競技における成績や功績が最大の注目点になります。オリンピックや世界大会への出場歴、チームのキャプテン経験などがあれば、必ず紹介文に盛り込みましょう。
同時に、シビアなトレーニング環境やメンタル面の強化方法など、ビジネスパーソンにも役立つ考え方を持っていることが多いので、その点を強調すると一層興味が高まります。
スポーツ選手の講師紹介例
本日の講師、〔講師名〕 さんをご紹介いたします。
〔講師名〕さんは、〇〇競技の選手として長年にわたり第一線で活躍され、
オリンピックや世界大会、国内リーグなどで数々の実績を残してこられました。
特に、〔主な実績・記録〕など、印象的な功績をお持ちです。
現役時代からリーダーシップとチームワークを重視され、
キャプテンとしてチームをまとめ上げた経験もお持ちです。
引退後は、指導者・解説者・講演活動などを通じて、
スポーツで培われた「挑戦力」や「メンタルの整え方」を発信しておられます。
本日は「〔講演テーマ〕」というテーマで、
トップアスリートとしての経験から学んだ、挑戦を続ける力と心の在り方についてお話しいただきます。
それではご登壇いただきましょう。
元〇〇選手、〔講師名〕 さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
大学教授・専門家の講師紹介例
研究分野や職歴がアカデミックな専門家の場合は、所属する大学や研究機関と、具体的な研究テーマを示すことが大切です。特に論文発表や受賞歴、メディアへの寄稿歴などがあれば、信頼感が増します。
内容が難しくなりがちな場合でも、一般の聴衆に向けてわかりやすい言葉を使用している専門家の例を示すと、より親近感を持ってもらうことができます。
大学教授・専門家の講師紹介例
本日の講師、〔講師名〕 さんをご紹介いたします。
〔講師名〕さんは、〇〇大学〔学部・学科〕の教授として、
〇〇(例:心理学・経済学・教育学・環境工学など)の分野を専門に研究を続けておられます。
長年にわたり、〔研究テーマ・専門領域〕について多くの論文や著書を発表し、
その研究成果は国内外で高く評価されています。
また、テレビや新聞、講演活動などを通じて、
専門的な内容を一般の方にもわかりやすく伝える取り組みを続けておられます。
専門家としての知見と社会的視点を兼ね備えたお話は、
聴く人の理解を深め、気づきを与えてくださいます。
本日は「〔講演テーマ〕」というテーマで、
日常生活やビジネスにも役立つ最新の研究成果と、その実践的なヒントをお話しいただきます。
それではご登壇いただきましょう。
〇〇大学教授、〔講師名〕 さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
講師紹介文を作成するときの注意点

講師紹介文を作成するうえで避けたいトラブルや、正確さを保つためのコツをまとめました。
講師紹介文はイベントの顔ともいえる存在です。ちょっとした不注意で誤った情報や誇張表現が含まれれば、講師や聴衆からの信頼を失う恐れがあります。
また、肖像権や許諾関連のルールを知らずに画像や動画を使用するとトラブルにつながりやすいため、情報や素材の取り扱いは慎重に行いましょう。
Wikipediaやネット情報の無断引用は厳禁
インターネット上には多様な情報が溢れていますが、出典不明の書き込みや口コミレベルの情報を無断で使用すると、講師紹介の信用性が低下します。特にWikipediaの内容は頻繁に更新されているため、古い情報を引用してしまうリスクもあります。
正確性を担保するためには、講師本人または公式サイトから取得した情報をベースに紹介文を組み立てることが大原則です。
誇張表現・誤情報に注意する
講師をより魅力的に見せようとして、実績や評価を実際以上に大きく書いてしまうことは避けましょう。後に受講者や関係者が事実関係を調べて矛盾が生じた場合、イベント全体の信用が大きく損なわれてしまいます。
評価や実績を伝える場合は、秀でているポイントを正確かつわかりやすくまとめ、誤解を与えない表現を選例することが大切です。
講師の許可を得て画像・動画を使用する
画像や動画などの素材は、講師紹介をより魅力的にする効果的な手段です。しかし、肖像権の問題や無断使用のリスクがありますので、事前に講師や所属事務所の許可を得ることが大切です。
特に芸能人や著名人の場合は、公式サイトやマネジメント事務所が提供する素材のみを使用し、常に最新の利用規約を守るようにしましょう。
紹介文は必ず講師本人に確認を取る
作成後の紹介文は、必ず講師本人や事務所に確認してもらうようにしましょう。経歴や肩書きに細かい修正が必要な場合は、適宜反映させます。
こうした確認を怠ると、誤情報が広まったり講師との信頼関係が損なわれたりする可能性があります。事前のチェックを徹底し、トラブルを回避することがプロとしての基本的な姿勢です。
講師紹介を成功させるための準備

事前にしっかり準備をすることで、本番の講師紹介をスムーズに進めることができます。
講演やセミナーで失敗しがちなポイントとして、紹介文を読み上げるときの練習不足が挙げられます。声に出してみると想像以上に噛みやすい単語があったり、イントネーションに迷う部分が出てきたりするものです。
また、講師とのコミュニケーションを密に取ることも大切です。日程や内容の最終調整をすることで、当日の段取りがスムーズになり、講師本人の安心感にもつながります。
司会練習と声に出して読むリハーサル
講師紹介の文章を作成したら、司会担当は必ず声に出して何度か練習を行いましょう。実際に読み上げることで、文章のテンポや聴き取りやすさを確認できます。
特に難しい専門用語や人名など、発音に注意が必要な箇所はあらかじめ講師に確認するか辞書で調べると安心です。
スライドや動画の活用ポイント
スライドや動画を用いた講師紹介は、参加者の視覚に訴える効果が高いため、インパクトのある演出が可能です。ただし、文字数が多すぎるスライドや長すぎる動画はかえって集中力を失わせてしまうため、適度な長さやシンプルな構成を心がけましょう。
講師の写真、活動実績のグラフや図などをわかりやすく配置すると、聴衆のイメージが鮮明になることが期待できます。
講師へのヒアリングと事前擦り合わせ
事前に講師からヒアリングを行い、経歴や活動内容の詳細、当日に伝えたいメッセージを確認しておくことで、紹介文と講演内容の齟齬を防ぐことができます。ヒアリングの際には、どのトピックに重点を置くかを話し合い、紹介文にも反映させるとよいでしょう。
もしオンラインであれば、事前に通信環境や使用プラットフォームの動作を確認するなど、細かな点まで準備を整えることで当日のトラブルを大幅に減らせます。
ウェビナーやオンラインイベントでの講師紹介

オンラインでの講師紹介には特有の配慮が必要です。注意点を押さえておきましょう。
ウェビナーやオンラインイベントでは、画面共有を活用して資料や映像を見せながら講師紹介を行うケースが増えています。しかし、回線速度や音声トラブルなど対面イベントでは起こりにくい課題もあるため、事前に対策を講じておくことが鍵です。
例えば、講師紹介動画を流した後に画面切り替えがうまくいかない場合、進行が滞り参加者の集中力が途切れる原因にもなり得ます。小さなオペレーションミスを防ぐためにも、当日の進行台本をしっかり準備しておきましょう。
スライド共有の際の注意
オンライン上でスライドを共有するときは、一瞬でも“隠したい画面”が映らないように注意する必要があります。事前に不要なウィンドウやタブを閉じておくことが安全策のひとつです。
また、スライドを切り替えるタイミングと話の流れをしっかり合わせるようにリハーサルしておくと、本番で落ち着いて進行できます。
オンライン配信での講師紹介動画の使用
講師紹介動画を用いる場合は、事前にファイルサイズや音量をチェックし、視聴者側で問題なく再生可能な状態にしておくことが重要です。著作権に関わる音源を使用する場合は、利用許諾を取得するかフリー素材を使うなど適正な対応を行いましょう。
動画の長さがあまりにも長いと、参加者の集中力が途切れる原因になるため、通常は1〜2分程度におさえるのが好ましいとされています。
司会者と講師の連携を円滑にするポイント
オンライン上では、司会者と講師がタイミングを合わせることが難しい場合があります。チャット機能やプライベートメッセージなどを利用して、合図を送る方法をあらかじめ確認するなど、細かな連携方法を決めておきましょう。
また、接続テストや音声確認を直前に行っておくと、お互いが安心して講演や進行に集中できます。リハーサル段階での綿密なコミュニケーションが成功への近道です。
デザイン面で押さえておきたいポイント
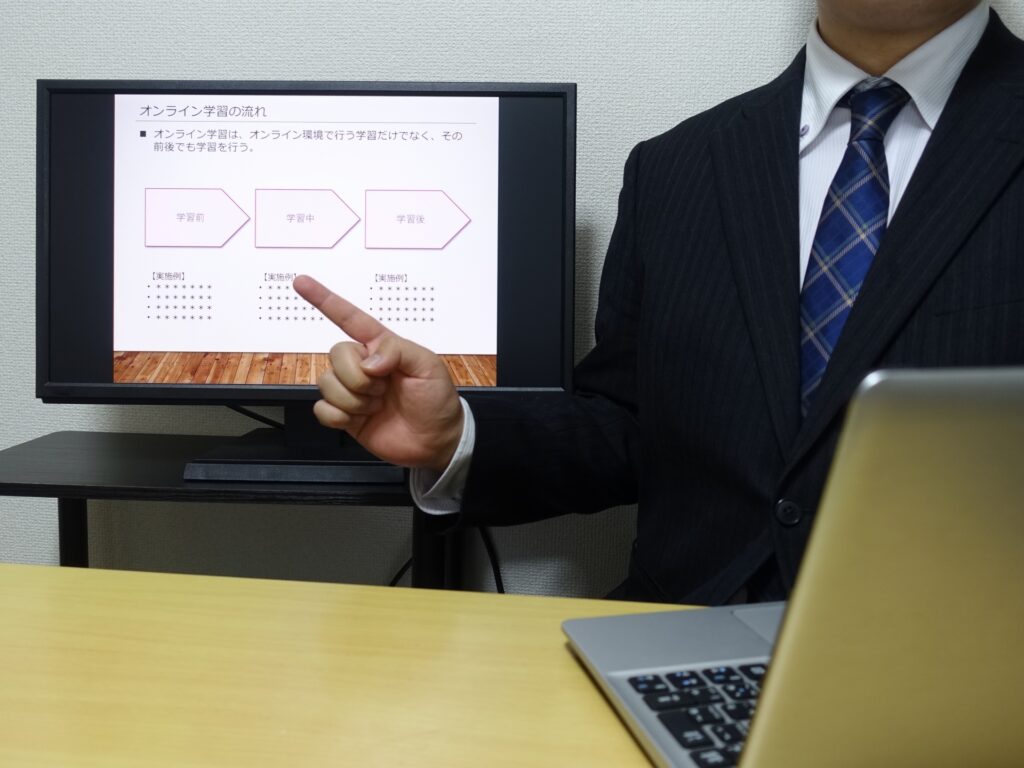
講師紹介スライドのデザインを工夫するだけで、参加者の印象や理解度は大きく変わります。
視覚的にわかりやすい講師紹介は、会場やオンラインを問わず、聴衆の興味を惹きつける効果があります。一方で、情報量が過剰になりすぎると見づらくなり、重要なポイントが埋もれてしまう可能性があるため注意が必要です。
デザインと内容が合致していなかったり、配色が不適切だと、せっかくの情報も十分に伝わりません。参加者にとって見やすいレイアウトと色使いを心がけましょう。
見やすいスライドのレイアウト
情報を配置するときは、視線の流れを意識して構成しましょう。例えば、左上から順番に要点を読み取れるようにすると読者が疲れにくくなります。大事な要素には大きめのフォントや目立つ色を使うとメリハリがつきます。
テキストを詰め込みすぎると、読み手がすぐに内容を把握しにくくなります。複雑な内容の場合は、図やアイコンを活用した視覚的サポートが効果的です。
文字サイズ・配色・フォント選びのコツ
スライドで読みやすい文字サイズは24ポイント以上が目安と言われています。視認性の確保のためにも、小さすぎる文字を多用しないよう注意しましょう。
配色に関しては、背景色と文字色のコントラストを強めに設定すると、遠くからでも見やすくなります。フォントは装飾性の高いものよりも、シンプルで画面表示に向いたものを選ぶと良いでしょう。
写真やイラストの活用と著作権への配慮
講師の写真やイラストを適切に使うことで、文章だけでは伝わりにくい雰囲気や人物像がより明確になります。ただし、肖像権や著作権の問題があるため、使用する素材は必ず許諾を得たものやフリー素材を利用しましょう。
著作権表示を行う場合は、画像の出典やクレジットをわかりやすく記載しておくとトラブルを防ぎやすくなります。必要があれば講師本人に確認を取り、画像の使用条件をクリアにすることが大切です。
候補に入れた講師一覧の作成・管理方法

複数の候補講師を同時に管理するためには、効率的なリスト化と優先度の設定が鍵となります。
イベントごとに全く異なる専門分野やイメージの講師を選ぶ場合、候補者のリストをスプレッドシートなどのツールで体系的に管理しておくとスムーズです。どの候補がどの分野に強いのか、スケジュールの都合はどうなっているかを見やすくまとめましょう。
管理がしっかりしていると、急な日程変更や追加オファーにも柔軟に対応できます。特に大規模イベントの場合、候補講師の情報をチームで共有できる仕組みを作っておくことが重要です。
候補講師を選定する基準と優先順位
講師を選定する際は、イベントのテーマや受講者層との相性、知名度、予算、スケジュールなど多角的に考慮しましょう。全てが完璧に合致するケースは少ないため、最優先項目を明確にしておくと決定がしやすくなります。
例えば、専門性を最重視するのか、集客力を重視するのかで選定基準が変わります。これにより候補者リストの並び替えや優先度設定がシンプルになり、早期に正式オファーが行いやすくなります。
講師派遣サービスや検索サイトの活用
自力で講師を探す時間がない場合や、より幅広い分野から講師を見つけたい場合は、講師マッチングサイトや講師派遣サービスの利用が便利です。検索条件を設定すれば、専門分野や講演実績などから候補を絞り込みやすくなります。
ただし、掲載情報の正確性や更新頻度には差があるので、最終的な判断をする前に講師の公式情報を再度確認するのを忘れないようにしましょう。
効率的に講師を見つけたい方へ
弊社の講師派遣サービス「Hitonova(ヒトノバ)」なら、条件を伝えるだけで最短即日で候補をご提案します。
探す・比較する・交渉する——すべてワンストップでサポート。
→最適な講師を無料で提案してもらう
講師決定後の連絡・日程調整のポイント
候補の中から正式に講師を決定したら、速やかにイベント日時や内容、報酬などの詳細を伝達します。細かい事項でも認識違いがあると後々トラブルになるので、メールやチャットなど文章でやり取りを残しつつ確認することをおすすめします。
また、日程調整では「確定」「仮押さえ」の区別を明確にしておくと、ダブルブッキングを避けることができます。必要であれば定期的なリマインドや事前打ち合わせも実施すると安全です。
【まとめ】講師紹介で伝わる印象と今後のヒント
講師紹介を通じて与える印象は、イベント全体の評価を左右します。効果的に行うための総括と次のステップを提示します。
講師紹介は、単に経歴を説明するだけでなく、イベントの狙いと講師の魅力を同時に伝える重要な役割を担っています。適切な情報収集と正確な原稿づくり、そして演出やデザインへの工夫が相まって、初めて魅力的な講師紹介が完成します。
しかし、一度紹介文を作ったからといって、それが最終形ではありません。講演のテーマやターゲット、環境が変われば、紹介方法にも都度変化が必要です。今回紹介したポイントを押さえつつ、常に最新の情報と工夫を取り入れることで、より良いイベント企画へとつなげられるでしょう。
最終的には、講師がどのように語りたいのか、参加者が何を求めているのかを意識したうえで、双方にとって最適な講師紹介を形作ることが大切です。質の高い講師紹介がイベント全体を引き立て、今後の開催にも良い効果をもたらすでしょう。
この記事のまとめ
・講師紹介は、イベント全体の印象を左右する重要な要素です
・紹介文には、講師の経歴や実績、専門性を正確に盛り込むことが大切です
・情報は公式サイトや本人確認済みの内容を使用し、誤情報や誇張表現を避けることが望ましいです
・司会者や講師と事前に内容やタイミングを共有し、スムーズな進行を心がけることが重要です
・スライドや動画を活用する際は、著作権・肖像権に十分配慮する必要があります
・オンラインイベントでは、通信環境や資料共有の確認を事前に行うことが効果的です
・一度作成した紹介文も、講演テーマや対象者に合わせて定期的に見直すことが望ましいです
・丁寧で正確な講師紹介を行うことで、講師の魅力を最大限に伝え、イベントの満足度を高めることができます
Contact お問い合わせ
講師選びでお悩みの方には、目的・ご予算に合った講師をご提案します。
気になる講師のスケジュールや講演料についても、お気軽にお問い合わせください。
5営業日経過しても返信がない場合は、
恐れ入りますが電話かkouen@scg-inc.jpまでメールでお問い合わせください。

